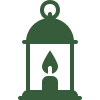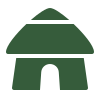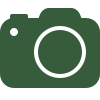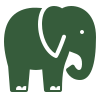次回にご期待ください。
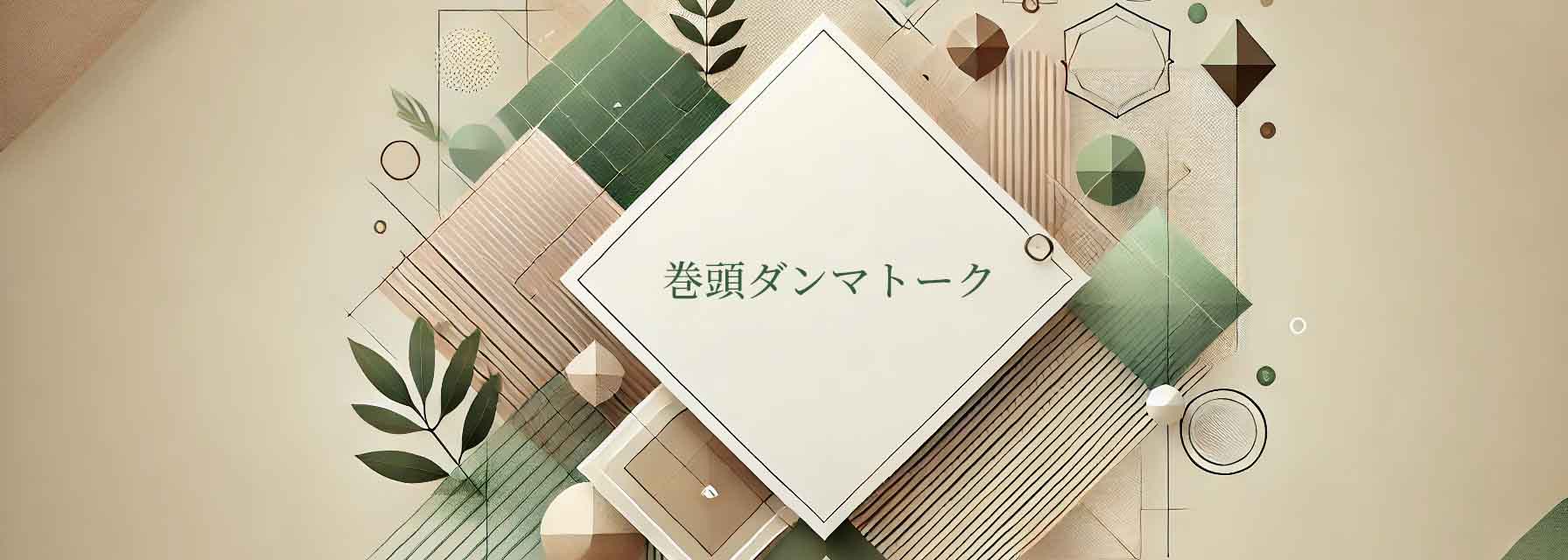
今月はお休みします

瞑想って、凄い!第2回
オンライン講座を通して
話は戻り、『ブッダの瞑想法 ヴィバッサナー瞑想の理論と実践』とグリーンヒルのYouTubeを見ながら瞑想を始めて3~4ヶ月が経った頃、朝日カルチャーセンターのオンライン講座に思い切って申し込みをしてみました。こんな初心者が受けて大丈夫なのだろうかという思いもありましたが、先生は初参加の私に優しく話してくださいました。九州在住で瞑想会への参加が難しい私にとって、ヴィバッサナー瞑想者の皆さんとの唯一の出会いの場であるオンライン講座が月1回の楽しみとなり、それから毎月受講しています。毎日一人で瞑想をしていると、わからなくなったり、やる気がなくなったりするときもあります。そんな私にとって、瞑想修行における質問ができる大切な月1回。先生と皆さんの顔を拝見し、次のオンライン講座まで、また1ヶ月頑張るぞ!!という私の瞑想修行のモチベーションを上げてくれています。講座内での先生ご自身の体験談、皆さんが瞑想や日々の生活の中で抱えていらっしゃる悩みへの回答は、私にとって有意義な話が多く、大変勉強になるものばかりである上に、自分自身の甘えを再確認できる場になっています。
ある月のオンライン講座で、先生が私には内観が必要だと勧めてくださいました。そこですぐに内観の申し込みをすることにしました。
1日内観と1ヶ月間のEメール内観
私は小さい頃から母のことを好きという感情がないと思って生きてきました。むしろ好きではないと思って生きてきました。母は私を大切にしてくれているけれど、私のことを好きではないのだろうと感じていたのです。幼い頃、他のみんながお母さん大好き!と抱きついているのに、私は一度もそんなことをした記憶がありません。母に対しては、弱いところを見せてはいけない。迷惑をかけてはいけない。手伝わなければならない。いい子でなければならない。ただそう思っていました。6歳の時まで泣き虫だった私が、母と二人暮らしになることが決まった時「何があっても、もう泣かない」という誓いを自分の中に立てたことだけは覚えています。それからは先ほど書いたように知らず知らずにいい子を演じていたのでしょう。
結婚してからはさらに母への嫌悪感が増し、母のやることなすこと、母の話し方、笑い方まで何もかもが嫌になっていきました。母を心配したり、あれこれ世話を焼いたり、ご飯を持って行ったり、我が家に招いたり、子どもたちの学校行事や習い事の発表会に誘ったり、いろいろ買って持って行ったり。母のことが気になり自分からいろいろするくせに、どうして嫌悪感しか抱けないのか。母一人子一人で育ててもらった母に対して、このような感情しか抱けないことが悲しくて、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。しかしたとえ母が何をしてくれても、どうしても母を目の前にすると嫌悪感しか出てこなかったのです。そんな自分が本当に嫌で仕方なく、責め続けた苦しい日々でした。
母への内観の1度目は表面的なことだけしか感じられなかったように思います。しかし2度目、3度目になると、母に愛してもらっていたことだけでなく、自分が知らず知らずに心の奥に蓋をして閉じ込めていた感情が溢れ出て、どうしても母を好きになれなかった理由が、幼い頃自分を守るために私が私自身に思い込ませ捏造した感情だったのだと気づかされ、母への感謝や申し訳なさを心から感じることが出来ました。何より母への嫌悪感が減ったような気がします。また今までいろんなことに対する感謝だと思っていた感情が、いかに上辺だけのものだったかということにも気づかせていただきました。
まだまだ表面だけの気づきではあると思いますが、内観後は他者への心からの感謝が深まり、相手を否定することが激減したのは確かです。相手の行動原理や価値観が自分とは違うだけなのだと考えられるようにもなったと思います。そのおかげでしょうか、今まで気づかなかった周囲の人の素敵な部分が見えるようになりました。
母に対する嫌悪の感情も完全消滅にはまだまだだと思います。日々の自己内観を続け、時期を見て集中内観に行こうと思っています。(続く)

八ヶ岳

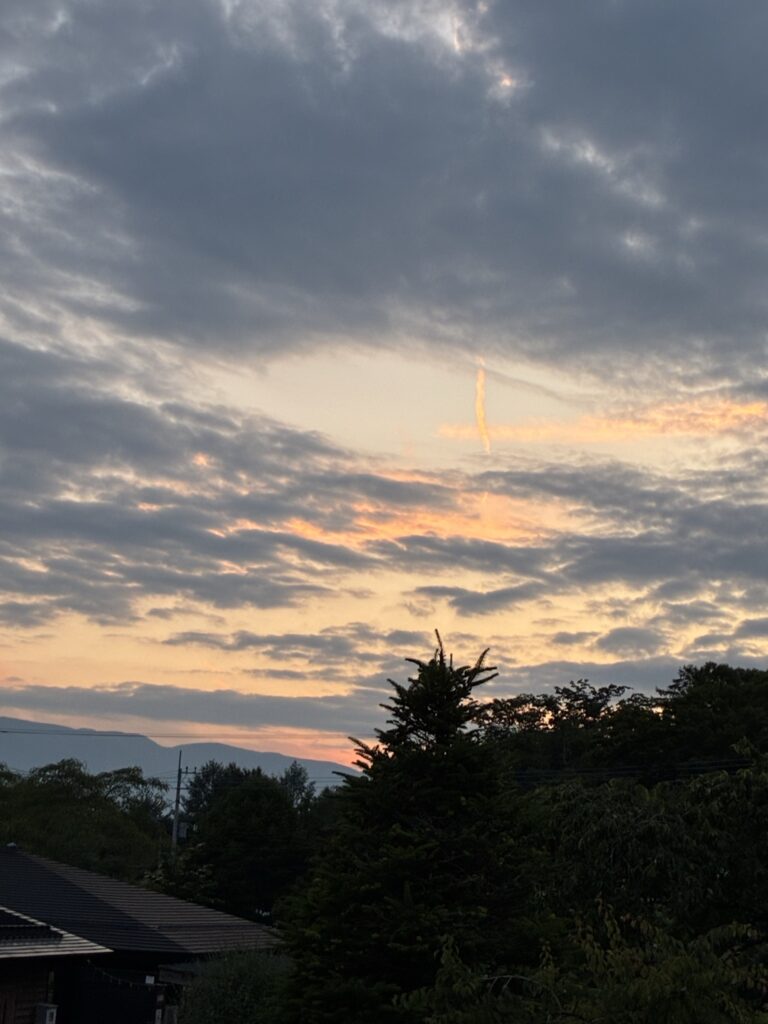


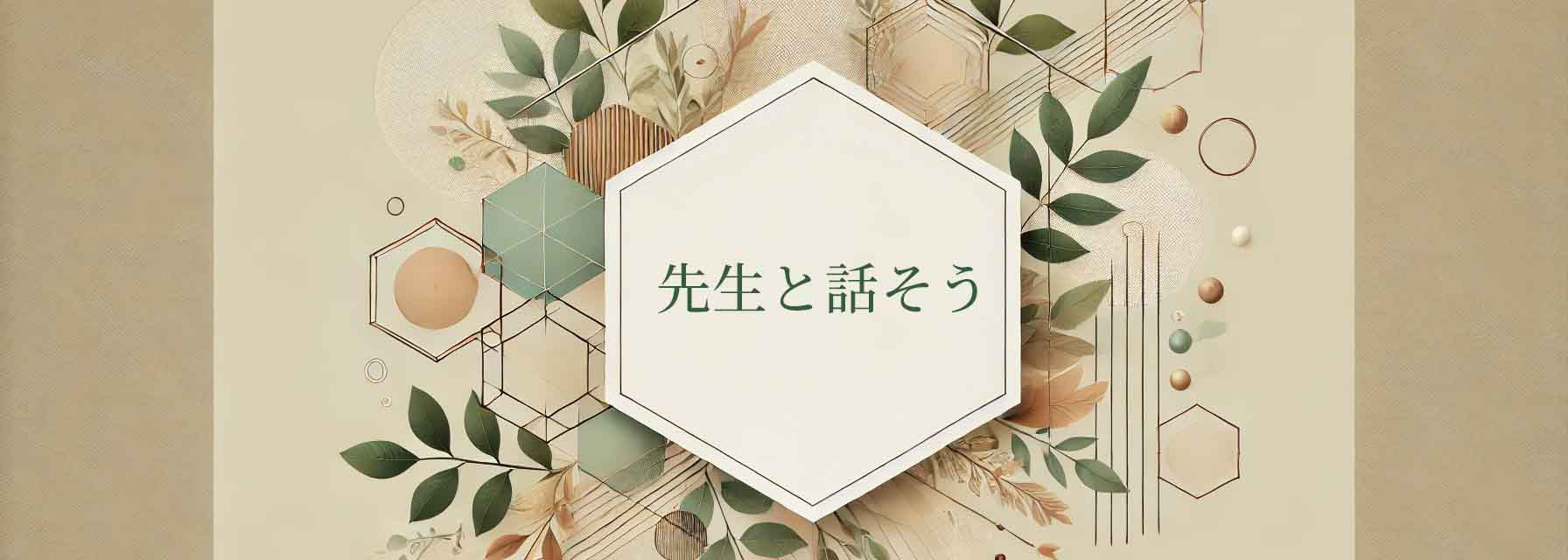
瞑想のご利益 第2回「酒か、瞑想か…」
ヴィパッサナー瞑想をしたらどんな〈ご利益〉があるのかという、誰もが考える、しかし、真っ正面から先生にぶつけるのは大いに気が引ける質問をあえてしてみようという主旨ではじめた対談の二回目。前回、ヴィパッサナー瞑想をすれば、どんな人でも集中力があがり、メタ認知能力が向上するという保証をいただいたので、もうじゅうぶん満足したのですが、そこでは終わらなかったのです。軽めの話題を選んだつもりが大変なことになりました。
まず、ヴィパッサナー瞑想をすれば、最初から、サマーディとサティの訓練をすることになる。その結果、戒定慧でいえば、定(集中力)と慧(洞察智)が高まっていくので、集中力が増し、アイディアが閃くことも増えていく。しかし……というところから今回の会話ははじまります。
戒定慧の三学とともに
榎本 つまり、サマーディの集中とサティの洞察だけでは充分ではなく、戒定慧の「三学」に則って瞑想しなければならないと言うことになりますか。
地橋 はい、その通りです。ヴィパッサナー瞑想は戒とともに歩んでいく瞑想なのです。
榎本 戒は、五戒(殺さない・盗まない・不倫をしない・嘘をつかない・酩酊しない)と理解してよろしいですか。
地橋 まずはそうです。「ブッダの瞑想法」は戒が基盤なので、初心者の方には、「五戒を守りたくない方は、どこかよそで瞑想してください」と伝えます。
榎本 あの、先生は戒律を守ることも瞑想だとおっしゃりたいのですか。
地橋 その通りです。朝日カルチャー講座の初回では必ずヴィパッサナー瞑想の大きな構造を説明しますが、「善行の瞑想」と並んで「五戒の瞑想」と呼んでいます。これは私の瞑想理論に基づく呼称に過ぎませんが…。
榎本 そうなんですか、初めて聞きました。
地橋 五戒を守ろうとする瞬間、マインドフルでなければ結果的に守れませんからね。善行をする一瞬一瞬も、上から目線の傲慢な心や物惜しみの心、打算や自己陶酔の心などによく気をつけて、サティを入れながら行為するので「善行の瞑想」なのです。
榎本 なるほど。先生はいつも「人生全体が瞑想である」とおっしゃってますね。
地橋 戒はパーリ語では「sīla(シーラ)」というのですが、榎本さんが英訳するならどんな語を当てますか?
榎本 え、戒なんだとしたら、commandmentとかruleではないかしら。それともtaboo?
地橋 これをvirtueと訳している文献がありました。
榎本 virtue…徳? ですか。
地橋 はい、タイの僧院でそれを読んだとき、感動しましたね。戒はたんなる行動規範ではなく、徳の修行だったのか。「人格完成の総力戦」として理解しなければならないということです。
榎本 たしかに、そこまで大きい目標となると、五戒だけでは不充分ですね。
地橋 そうなんです。戒(シーラ)をただ単に〈禁止事項〉と捉えるのは極めて浅薄な理解です。
榎本 (そんなこと言われてもという気持ちはありつつ……)わかりました。では、あえてお訊きしますが、マインドフルネス瞑想ではシーラ(戒)を無視し、サマーディとサティだけで押し進めますよね。このマインドフルネスと、戒を前提にしたヴィパッサナー瞑想とは、瞑想の効果という点ではどのように変わってくるのでしょう?
地橋 気づきやメタ認知の効果は同じと考えてよいですが、ヴィパッサナー瞑想では「戒の瞑想」を実践することによって、カルマがよくなり人生が必ず好転します。戒とは、他人に苦しみを与えないことです。万引きしていた人がそれをやめる、嘘をついていた人が嘘をつかないようにする。自分の未来に苦の種をばらまくことをやめるのですから、人生がよくならないわけがない。
榎本 しかし、現実問題、グリーンヒルで瞑想し始めたとたんに、みなさん、スパッとやめられるものなのですか。特に飲酒などは。
地橋 不飲酒戒だけは徐々にやめればよい、と伝えています。酒か瞑想か、と二者択一を迫れば、どちらを取るかは明白ですから。
榎本 まず瞑想に引き込んで、瞑想から離れられなくさせてから、酒を止めろと言うわけですね。
地橋 そうです。(笑) 瞑想が進んでくれば、必ず飲まなくなります。瞑想の素晴らしさを体験すれば、アホらしくて、酔っ払っていられないと気づくのです。
榎本 わかります。
地橋 飲酒の戒は、自分に苦を与えないためです。酔えば、抑制系の心が働かなくなり、殺・盗・淫・嘘、なんでもアリになって、結果的に悪業の報いを受けて苦しむのです。その反対に、戒を守る人生に舵を切ったならば、自動的にカルマがよくなります。確実に幸福度が上がることを誰でも検証していきます。因果論・業(カルマ)論が、原始仏教の根本であることを肝に銘じてください。
榎本 つまり、今回の話題に沿って言えば、因果応報のこの世では、仏教の倫理性ゆえに、悪因悪果の可能性を孕んだマインドフルネスよりも〈ご利益〉は大きい、と。
地橋 そういうことです。
榎本 しかし先生、あえて申し上げますが、その理論はこの世間に通じますかしら? 戒を徳と捉えるのは、僕も目を開かれる思いがしました。ただ、やはり我々のような在家で瞑想をしている者は、これを禁止事項と捉え、禁欲の勧めだと理解するのはやむを得ないところもある気がします。また、禁欲は人生を味気ないものにしてしまうという考え方もあります。僕自身は完全に酒を断ちましたが、酒席には出ます。1Day合宿に出ておられる方も言っていましたが、職場の仲間との飲みの席で一杯も飲まないと、同僚らにさみしがられるとおっしゃっていましたね。僕も最初のころは「つまんないな」と言われたりしました。テレビをつければ、お酒を飲む人生というのはなんて楽しいんだろうというCMがバンバン流れているわけです。そんな中で、戒を厳しく守って生きることは、人生を貧しくすると考える人もいるのではないかと思うのですが。
地橋 幻想ですね。まだ手に入れていないものは甘美に思えてしまうのが、マーラ(悪魔)の仕掛た罠なのです。現実は苦(ドゥッカ)なのに、妄想は常に甘美なのです。夜の街にくり出していくときが最高で、店に入れば雰囲気が悪かったり、口論になったり、ボラれたり、失望することが多く、現実には苦の本質が潜んでいるのです。
榎本 でも、気の合った仲間と本当に楽しい宴を張ることもあるのでは…?
地橋 楽しいので、思いっきり飲んで、食べて、翌朝、二日酔いの頭痛と吐き気で苦しむというわけですね。
榎本 (自分はそこまで深酒をしたことがないぞ、と思いつつも黙っている)。
地橋 心ゆくまで貪って、怒って、ボコボコにしたら、どんなに気持ちがいいだろう…と錯覚するのが人間です。仏教は貪・瞋・痴を抑止する引き算の幸福原理です。
榎本 引き算?
地橋 俗世の幸福原理は足し算です。できるだけ多くの快楽を味わい、価値あるものを手に入れれば入れるほど、幸福度が上がると考えています。快楽に耽れば耽るほど、より強い刺激を求めて感覚がただ爛れていくし、甘いものを食べれば食べるほど幸福になるのではなく、メタボになり、糖尿病になるのです。
榎本 「たとえ貨幣の雨を降らすとも、欲望の満足されることはない」というヤツですね。
地橋 そうです。人は所有しているものに縛られるんですよ。大事なものを奪われ壊されれば、烈火のごとく怒り、掛けがえのないものを喪失して悲嘆に暮れるのです。「渇愛」という名の執着が強まれば強まるほど、苦の分量が増す法則です。欲望は「不満足性」の別名であり、足し算は苦に向かっていくのですよ。
榎本 うーむ。
地橋 一方、仏教では、欲望も怒りも手放せば、苦から解放されていくという引き算の幸福原理です。幸せを求めて結婚し、幻滅と離婚の苦を経験する人も多いですが、良い夫婦になればなったで、配偶者を喪った悲痛なドゥッカ(苦)は凄まじいものです。愛妻に死なれた直後に後追い自殺をした文芸評論家がいますが、執着の度合いと苦の度合いが比例する事例と言えるでしょう。
榎本 だから、五戒を守ることは、欲望を抑止して、執着を手放すことであり、苦しみを引き算していくということですね。
地橋 そのとおりです。殺生戒は怒りの抑止であり、盗みも不倫も飲酒も欲望系の引き算となり、真実を偽る嘘は解脱の可能性を破壊する。すべて人を不幸に導くものです。その欲と怒りの衝動から守られるので、五戒の瞑想にはご利益があるというわけです。
榎本 引き算の手放しだけでは、ちょっと寂しい感じもしますが、おっしゃるとおりではあります。
地橋 より高いものを知って、より低いものを捨てる法則を心得なければなりませんね。「つまらぬ快楽を捨てることによって、広大なる楽しみを見ることができる」とブッダも説かれています。欲しいものをゲットした瞬間の卑しい利己的な快感よりも、人のお役に立てた瞬間の幸福度がはるかに高いことは心理学的にも証明されています。欲望を満たすことはつまらぬ快楽であり、より高い、崇高な楽しみを知る智慧の瞑想が実践されるべきです。
榎本 (やはり、ちょっと講演会モードになってしまったなあ…と思いつつ) はい。がんばります。今回もありがとうございました。

2025年8月号
(1)
★日が暮れかかった頃、近隣の沼の畔を散策した。
何の変哲もない水面が夕陽に照り映え、異様な輝きを帯びて、刻一刻と化けていく…。
あるがままの法としての存在は見がたく、脳内フェイクの印象に執着し、最期までダマされ、空(す)かされ、誑(たぶら)かされながら、また死んでいくのか……。
……………………
(2)
★肉眼で見た世界は、写真のようなフレームも構図も何もない空間の拡がりに過ぎない。
視覚を最初に直撃したものが、「乱反射する夕陽」「湖面にさざ波を刻んでいく風」と認識された瞬間、概念化されてしまう。
写真の美しい色や輝きが一度心に焼き付くと、事実は消え失せフェイクしか残らない……。
……………………
(3)
★自分が何をやってきたのか、何を話し、どんなことを考えてきたのか、自分の人生そのものだった経験事象が朧(おぼろ)になり、やがて忘れ去られていく…。
のみならず、心に焼き付いたはずの記憶が修正され、リメイクされ、事実とかけ離れた妄想のドラマに変容し、エゴの脳内劇場で再演されていないか……。
……………………
(4)
★大嫌いな人、かけがえのない家族、無二の親友…がいるのだろうか激怒したり、安らぎを覚えたり、癒された一瞬一瞬に作られた過去の業が、その日その瞬間の経験事象として帰結しているだけではないか。
揺るぎない絆や犬猿の仲があるのではない。
業が生滅する束の間の事象の流れがあるだけということ……。
……………………
(5)
★真実であってもフェイクであっても、過ぎ去ってしまえば夢のようだ。
信頼の絆で結ばれていた掛けがえのない人も死に、毒々しい嫌悪の念を向けてきた人も死んだ。
愛も信頼も尊敬も嫌悪も軽蔑も…事実が歪曲されて編集されたエゴの脳内劇場。
もう猿芝居を止めたいのだが、幕が下せず立ち尽くす日々……。
……………………
(6)
★自分がこれまでに犯してきた罪業の数々、激怒した瞬間、暗愚な思考…その全てが形成した業を思えば、地獄行きだろう。
心から人のために力を尽し祈りを捧げ、寺に布施をし、懸命に瞑想した一瞬一瞬の業は、天界への再生に通じるかもしれない。
地獄も、餓鬼も、畜生も、修羅も、人間も、天も…、もう、因果に縛られた業の世界は、うんざりだ……。
……………………
(7)
★苦受を受け楽受を感じているのはこの「私」だ…という印象は、エゴ妄想に過ぎない。
なるほど、「私」が苦しいのではなく、苦の事実があるだけか。
でも…、だから、どうだというのだ。
業の結果を受けた瞬間、否応なく反応して新たな業を作り続ける輪廻の流れを、これからも永遠に続けるのか……。

8月号
2025年の7月号をもちまして「ちょっと紹介を」の連載を終了とさせていただきました。長きにわたって筆を執っていただいた前編集長に心よりの感謝を申し上げます。
さて、今月号より新たな連載『瞑想 山小屋だより』がスタートいたします。筆者の恭子さんは、ファスティングなどにも取り組み、タイの森林僧院で約一ヵ月の瞑想修行を複数回おこなったりされている、グリーンヒルの中でも最も熱心な瞑想者のひとりです。そんな恭子さんが、本格的に瞑想に取り組むために、都会を離れ、八ヶ岳に庵を結ばれました。慌ただしい生活の中で、なんとか瞑想する時間をひねり出している僕にとっては、羨ましい限りです。では、その第1回「八ヶ岳の森林僧院」をお届けします。
八ヶ岳の森林僧院
山の朝は早い。5時には目が覚めてしまう。東京だとあと2時間は寝ているというのに。特にこの八ヶ岳エリアだけが早く日が昇るわけではないのに、どうしてだろう。多分山の気や、動物、木々、鳥たちが起き出す気配、または眠りにつく気配にこちらの気が影響されるのかもしれない。
軽く朝食を取ったら散歩に出かける。六門解放の歩く瞑想だ。坂道なので上がったり下ったり、足元も悪いし、草や木の根に躓きそうになるし、雨の後などは泥濘になる。淡々とアスファルトの道を歩いていた時とは別の緊張感がある。泥濘には大きな二つに割れた蹄の跡を見たりする。
偶蹄目、これは多分イノシシ。横に二つ縦に二つの足跡は多分ノウサギ。人には滅多にすれ違わない。鶯の声、カラスの声、名前も知らない様々な鳥の声。林を抜ける風の音。はるか遠くに車の音。「聞いた」「見た」「ひっかかった」「着」。でも時々美しい景色や音に心を奪われていることにも気づく。
この山小屋に引っ越してきたのは1ヶ月前の6月始めのことだ。それ以前は東京の杉並区に40年近く住んでいた。生まれたのもそこだから、時々出たり入ったりはあったものの、ほぼ70年近くを東京で暮らしてきたことになる。移住を決めた理由はひとつではないけれど、大きな理由のひとつは「瞑想をちゃんとやりたい」ということだ。
瞑想をするハードルを下げる。心が強い方々はどんな環境でも、どんな生活でもできるのだろうけれど、私のように周囲に流されやすく、暑さ寒さにくじ挫けやすく、雑音にすぐに気が散り、人間関係で気持ちが揺れてしまう人間は、まず環境を強引に整えてしまう方がいいと考えた。何しろもう残り時間は僅かしかないのだ。命はあったとしても元気でいないと良い瞑想は難しい。
実は、意外とこの決意は簡単だった。去年の暮れには決心して準備を始めていた。この山小屋と巡り合って手にいれたのは、もっと前の秋のことだ。最初はウィークエンドに山小屋として使うつもりだった。それなので実に小さい山小屋で、家の重心にチェンマイのお寺で頂いた仏像を置くと、まるでクーテイのような家なのだ。「ここで暮らしてもいいのではないか?」と思ってからはすぐに移住する気持ちが固まった。しかしそこからが大変だった。こんなに大変とは思ってもみなかった。
家を立てて40年弱、子育てをして、仕事もしていた家だった。捨てても捨てても物が出てくる。溜めこんだ物はまるで贅肉のようで、体や心に纏わり付く澱のように感じられた。それは単に「物」ではなくて、「物」に纏わる「プライド」であったり「愛しい思い出」であったり、要するに「執着」なのだ。「物」が捨てられないのではなくて、問題は「物」の裏側にしっかりと張り付いている感情の方だった。
自分の身体から引き剥がすように「物」を捨てていった。だんだん身軽になっていくと、自分が何者でも無くなっていく心もとなさが募っていった。自分が「こういう者だ」と何で思えたのだろう。そもそも何者でもなかったのに。「物」を捨てていくうちに、だんだん清々しい気分にもなっていった。その昔、ブッダに付き従って、出家した弟子たちは、糞掃衣と托鉢の鉢ひとつでその後の人生を生きた。すごいことだと改めて思う。まだまだ欲にまみれた私は、7割は処分できたものの結局色々なものを山小屋に持ち込んでしまった。まだまだである。
山小屋暮らしでは、他者の気配や音が無い。車の音もほとんどしないし、灯りも無いから夜は真っ暗。風の音、雨の音、鳥の声が聞こえるだけ。これがどれほど瞑想修行にプラスの環境か、住んでみるまで想像できなかった。やはり意思の弱い修行者には、外側の環境を整えること、内側の環境つまり健康やトラウマの解消が大切だと感じている。とは言うものの、この10年東京で、大家族で暮らし、騒音に悩まされながらも、毎日少しずつでも瞑想を続けてきたからこそ今があるのも確かなことだ。与えられた場所で淡々と瞑想を続けることでしか、先には進めない。
歩きの瞑想をしていたら足元を大きなトカゲが猛スピードで横切った。潰しそうになって蹈鞴を踏んで「わ!」と叫んでいた。偉そうなことを書いているが、トカゲを見た時から、つまず躓きそうになって叫んでしまうまで、Satiは全く入らなかった。「Satiが入らなかった」とSatiを入れた。本当にまだまだである。

グリーンヒル道場ベランダの石仏

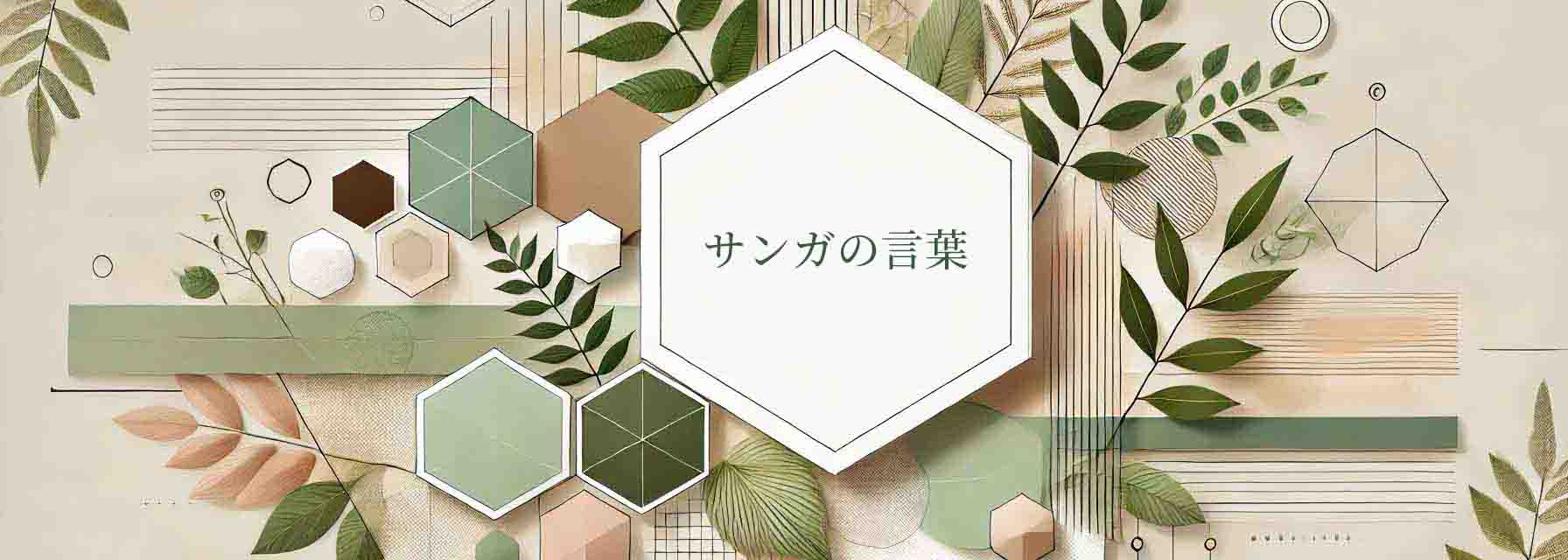
混乱から智慧へ(二)サンガの言葉 ニャーニャナンダ長老
2005年11月から2006年1月に掲載されました。今月はその第2回です。
4.最高の自由
自由と責任は二重拘束として切っても切り離せません。この世のあらゆる段階の自由は、ある程度の責任と結びついています。権利と特権は責任と義務を犠牲にしてのみ享受することができます。皆さんは自由ですが、義務に縛られています。
現世の状況における不調和は、私たちが資産に依存していることから起こります。あらゆる資産は、結局のところ、負債となります。まさに資産に対する獲得と保持そのものによって、私たちは縛られているのです。依存とは両方向のものです。私たちは資産に依存しているために、資産は私たちに最大の犠牲を要求するのです。
しかし、資産の無い自由はあるのでしょうか。ブッダは「ある」と言っています。ブッダはニッバーナを「無資産」(ニルパーディ“Nirupadhi”)と表現しました。これは、あらゆる資産の無い、この世を超越した自由です。五蘊(五つの集合体、すなわち色・受・想・行・識)はこの世の者達による資産だと見なされています。この世の者達は、資産に依存することによってアイデンティティとしての自我を得ています。
輪廻の存在は、これらの資産を増やしていく無限のプロセスです。しかし、悲劇は誰も資産を支配できないということなのです。ところが実際には、世間の人は惨めな奴隷状態を僅かな支配として自慢します。
この僅かな支配には、その割り当て分の責任が伴います。人は行為における三つの門、すなわち、身体、言葉、心においてなされる行為に対して道徳的責任があります。これに伴うカルマの絡み付きは、生、老、病、死、愁、悲、苦、憂、悩、そして苦諦に示されているその他のすべての苦と、延々と続きます。
この多重の苦から自由への道は、五蘊=「資産」を支配できるという考えは自惚れでしかないと理解すること、を通じて得られます。この理解によって、すべての資産の放棄へ至る厭離と離貪が生じます。このようにして、人はこの僅かな支配を放棄し、最高の自由、すなわち「無資産」を獲得するのです。
5.「アテンション・プリーズ」
ダンマの文脈において、アテンション(注意)とは、根源または発生源に対する洞察を通じて、物事の根源に到達することを目的とする「根本的注意」です。注意は、展望を散漫にしたり曇らせたりする、雑念という落とし穴を避けようとします。
この正しい種類の注意はマインドフル(*註)であることと、全面的な気づきと共にあります。マインドフルであり全面的に気づいていると、人は自分の注意を現在の瞬間に狭めることができます。
私たちの日常生活において、日常活動の些細な事に注意を払うことはめったにありません。注意は常に要求されるべきものです。私たちはかなり機械的に日常の仕事を行います。私たちの行為は大部分が衝動的なものです。通常の生活において、慣れきったやり方のほうが快適だと感じます。日常活動の些細な事に対する深い洞察を得るための隠れた潜在力は無視されます。
しかし、最も些細なものが最も深遠なものになることがよくあります。人は最も普通のことに注意を払うこと、すなわち呼吸や姿勢を変えることや生理的要求に答えること、などの日常生括の活動を見ることによって、この真理に目覚めます。根本的な注意によって一見些細な生活状況の中に、新鮮な洞察により常に新しい層を明らかにします。
注意の範囲は、サティパッターナ・スッタ(四念処経)に記されている四つの気づき(サティ)の基礎、すなわち身・受・心・法に対する瞑想に渡ります。注意が鋭くなればなるほど、基礎はより深くなります。
マインドフルな状態と全面的な気づきでスイッチを押された鋭い注意という「武装解除の光線」は、透徹する智慧の働きをします。これは、攻撃の受け流しと突きに熟練した剣士のように活発に動いて、マーラ(悪魔)の軍勢を寄せ付けません。
洞察の瞑想は注意を増して、多く出てくる思考の芽を摘むという原理で作用します。通常、注意は心の対象をつかめるほど鋭くはありません。注意は、思考の速度にはほとんどついて行くことができません。思考の根をつかむには、非常に注意深くなければなりません。注意深さが足りないと、思考は必ず飛び跳ねてどこかへ行ってしまいます。ですから、優れたテニスプレーヤーのように、「接触」のまさにその瞬間に注意というラケットを振らなければなりません。
しかし接触を熟知し理解して
平安を楽しむ人々は
実に接触がほろびるが故に
快を感ずることなく
安らぎに帰している (スッタニパータ 737 岩波文庫、中村元訳)
6.よき運転者たれ
私たちの人生を旅に例えてみましょう。体は車です。旅は四種類の動きすなわち、歩く、立つ、坐る、横になる――を通じてなされます。これは私たちが日常生活において繰り返し行っていることがらです。
よき運転者となるためには、事故を避けなければなりません。よちよち歩きの子僕の頃、まっすぐ歩けるようになるまでに何度も事故に遭いましたが、ブッダの唱えられた八正道をまっすぐ歩くにはよりいっそうの注意深い気づきが必要です。
私たちは「姿勢の交差点」で不注意な行動をしがちです。気づきのない状態に陥る「事故」を避けるためには、「姿勢の交差点」に気をつけなければなりません。姿勢を変えるときには、機械的、衝動的になりやすいものです。そのためには思考のスピードを落とし、注意力をより鋭くしておく必要があります。
「私は歩いている」と気づいて歩き、「私は立っている」と気づいて立ち、「私は坐っている」と気づいて坐り、「私は横たわっている」と気づいて横たわります。体が何かをしたいと思った時は、そのことに気づいていなければなりません。
輪廻という危険な道を車に乗って向こう見ずに進んできたために、私たちは多くの事故と死に出くわしてきました。これからは少なくともできる限り頻繁に「退却」しなければなりません。そのためには「姿勢の交差点」に気をつけつつ、ゆっくり、注意深くかつ常に気づきをもって四つの動作を行うようにする必要があります。このようにして私たちは、注意深さ(appamada不放逸)を育てることができます。これこそブッダが不死の道と説かれたものです。
気づきは不死への道であり
気づきがないのは死への道である
気づいている人は死に遭うことはない
気づきのない人は死んでいるのと同様である (ダンマパダ21節)
7.心を制御する技術
早い川の流れを堰き止めるには四つの努力が求められ、精力的に取り組まなければなりません。
1.流れている水を止める
2.そこに流れ込んでくる水を取り除く
3.ダム作りの基礎を築く
4.徐々にダムを建設しで補強・安定させる
早い思考の流れを堰き止めるにはやはり四つの努力が必要です。
私たちは以下のことをしなければなりません。
(1)不健全な思考が入ってくるのをチェックし抑止する
(2)生じてきた不健全な思考を捨てる
(3)まだ生じてきていない健全な思考を喚起する
(4)既に生じた健全な思考を補強・安定させる
努力の方法はいずれの段階においてもまったく同じです。常に真剣に集中して取り組むことです。抑制、放棄、発展、安定という四層の努力のためには、私たちは興味を喚起し、努力をし、精力的になり、決心を固め、精進のためにはあらゆることをしなければなりません。
これが智慧と解脱につながる八正道を完成するための正しい気づき(正念)と正しい集中(正定)を成長させる正しい努力(正精進)なのです。
アジタよ、この世にどのような流れがあろうとも
気づきをもって注意している
これが流れを抑止する方法であると私は説く
智慧によって堰き止められるのだ (スッタニパータ1035)
訳註:マインドフル(mindful)は、次の三つの意味を含んでいます。
(1)気づき (2)注意深さ (3)熱心さ
(文責:編集部)