(1)
★暮れも正月も、人間が妄想を共有しているだけで、法として存在している訳ではない。
時ならぬ梵鐘の音に八王子の裏山の狸が目を開いたかもしれないが、『除夜の鐘か・・』とは思わない。
「音」とサティを入れた人間に近いだろう。
宇宙にはいつだって、ただの事実が存在しているだけなのだ。
事実に苦しむのは致し方ないが、誤った認知と勝手な妄想で苦しむのは愚かしい。
法と概念を仕分け、あるがままに観る瞑想を修行する所以……。
……………………
(2)
★早稲田に所用があったついでに、近くの母校を50年ぶりに再訪した。
文学部は激変していたが、大隈侯の銅像と時計台は往時のままだった。
受験の下見に初めて訪れた高3の冬の夕方、真っ赤な夕陽を背景に、黒々と浮かび上がった銅像のシルエットが鮮烈に心に焼き付いた。
そのイメージが、瞑想に人生を捧げる発端になるとは知る由もなかった……。
……………………
(3)
★妄想する能力を得た人類は、甘く美しい未来を夢見ることによって、苦しい現実に耐え抜こうとしたのだろう。
美しい夕陽の大隈候銅像は、受験勉強のヤル気に火を点け、合格に導いてくれた。
そして入学後に、夢と現実のギャップに打ちのめされ、苦と渇愛の構造を学んでいく発端となった……。
……………………
(4)
★未来の夢だけではない。
失恋の痛手も、出産の激痛も、どんなに苦しかった記憶も、やがて風化し、美化されていく。
記憶を書き換え、甘美な未来を夢想させ、苦しい現実を誤認させる妄想が充満した人類の脳。
果てしない輪廻の流れを永遠に続けさせる無明の力……。
……………………
(5)
★徴兵令が布かれた明治22年、徴兵忌避者がなんと9割以上。
「日本」や「国家」という妄想に殉じて死ねる民はわずか数%だった。
だが、共同幻想を徹底教育して半世紀、特攻隊の若者が機体もろとも次々と自爆していった。
妄想に生き、妄想に死す人類……。

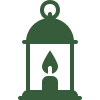 瞬間の言葉
瞬間の言葉