(1)
★原始仏教の要である四聖諦は、苦の現実、その原因、超克された境地、その最終点に達する8つの道である。
なぜ苦しくなるかを心得る第二命題は、因果論を正しく理解することだ。
だが、因果論を学び業論を肝に銘じても、こと自分の問題になるとその理解がブッ飛んでしまう。
エゴ妄想に圧倒されてしまうからだ。
自己中心的な生存欲に端を発する我執から目覚める瞑想……。
……………………
(2)
★夫婦喧嘩をしているという妻の話を聞くと、とんでもない夫だと同情する。
次に夫の言い分を聞くと、え、あの人そこまで自己チューなのか……と驚く。
物事を認知する瞬間、<選択的注意>が働いて情報の取捨選択がなされていることに気づかない。
エゴワールドが自動的に形成されていく構造。
……………………
(3)
★あの論理的なドイツ国民が、ナチスの愚劣な幻想を熱狂的に共有していた時代もある。
夫婦喧嘩をする人もしない人も、百人いれば百人の妄想世界。
自分は自分のエゴワールドに住しているに過ぎない、と気づけなければ、他人を非難し断罪したくなってくる。
人には真実は見られないのだ、と心得ておく……。
……………………
(4)
★先天的聾唖者が7歳で手話を覚えるまで、過去も未来もない今の瞬間だけに生きていたと証言している。
言語がなければ時間は発生しないし、記憶を司る海馬が損傷しても時の後先が失われる。
あるがままの法の世界に生きている動物達に知恵は生じず、言葉と時間の感覚を得た人類は妄想の底なし沼から出られない……。
……………………
(5)
★歴史を学び、夢と希望に向かう人もいるし、トラウマに苦しみ、将来不安の妄想で自滅する人もいる。
想像力を持たないチンパンジーは、「今、ここ」だけに心を使いきり、過去を恨まず、未来に絶望することもない。
妄想を止め、サルの脳で経験し、ヒトの脳でラベリングするヴィパッサナー瞑想……。
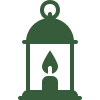 瞬間の言葉(今日のひと言 改め)
瞬間の言葉(今日のひと言 改め)
2025年12月号
(1)
★子豚を連想させる若い女性が、鉄板焼のハンバーグを仲よく食べながら、幸せそうにコロコロ笑い合っていた。
①美味しく食べられる。
②よく眠れる。
③人と心が通じ合う。
虐待で傷ついた人達にとっては、これが幸福の定義だという。
3つとも備えていながら「不満足性」という名のドゥッカに苦しむ普通の人達……。
失ってみて、初めて掛けがえのなさに気づくものばかりだ。
……………………
(2)
★自分の存在を否定され、誰からも認めてもらえなかったら、生きていけるだろうか。
人は、仕事をして褒められ、人の役に立ち、人に必要とされるから幸せを感じることができる。
……との理念から、知的障害者を全従業員の7割も雇用している会社がある。
幸福の原点は、基本的自尊感情と自己有用感……。
……………………
(3)
★町のパン屋のおじさんは「ご飯を食べて、働いて、安心して眠れ、普通に暮らしていける。それが幸せじゃないの」
「自由に物が言え、健康で、笑顔で、皆が仲が良いこと」を付け加える人。
何も求めなければ、ガツガツしないし、失望しないし、人と比べなくなるし、心が静かになるよ、と言う人……。
……………………
(4)
★人が求めてやまないものには、段階がある。
①水が飲め、物が食べられ、息が吸え、眠れる。
②安心安全が持続する。
③帰属する祖国、仲間、家族、居場所がある。
④承認される。重んじられる。敬われる。
⑤夢を叶え、理想を実現し、才能と可能性を最大に花開かせる。
⑥因果に縛られて変滅する繰り返しから解脱する……。
……………………
(5)
★快を貪り求め、多く所有するほど幸福度が上がると考える足し算の幸福原理は、何がなんでも生存し増殖しようとする生命の本質かもしれない。
だが、地球の資源にも人類の異常増殖にも上限がある。
仏教が提示してきた、欲望とエゴの引き算がもたらす静けさと優しさの価値を学ぶ時が来ている……。
2025年11月号
(1)
★瞑想対象に集中しようと必死になっていると、なぜか力んでいる自分の姿が俯瞰され、ハッと我に返ることがある。
サティが本来の機能を取り戻した瞬間だ。
集中にこだわり、ガチガチだった全身からフッと力が脱け、やわらかく緩んでいく。
この脱力の瞬間を「軽安」という……。
……………………
(2)
★人生が上手くいかないので、現実逃避のツールとして、瞑想にのめり込む人たちも少なくない。
集中力のあるタイプは、抑圧する力にも恵まれているので、ますますサマーディに溺れ込む。
そんな瞑想は「現世の楽住」に過ぎない。
煩悩を一つずつシラミ潰しにせよ、とブッダは言う……。(『削減経』)
……………………
(3)
★「法を拠りどころとし、他を拠りどころとするな」
ブッダが生涯の最後に説かれた遺訓である。
だが、法を拠りどころとせず、個人を崇拝し拠りどころとしてしまうのが世の常だ。
思わぬ人の口から、正しく法が説かれている瞬間にハッとすることもある。
山川草木の中に法を視る者もいる……。
……………………
(4)
★うるさい、臭い、痛い、損した、と苦受を受ける一瞬一瞬ごとに現象化した不善業が消えていく……。
楽しい、美味しい、儲かった、やったぜ!と楽受が続く幸福の日々の実状は、徳のポイントが恐ろしい勢いで費消されているのだ。
因果が織りなす業の世界では、不幸は負債の返済、幸福は貯金の切り崩し……。
……………………
(5)
★執着すれば人生が苦しくなる渇愛の構造。
だから「この世のことはの泡沫の如く、陽炎の如く視よ……」とブッダは言う。
そうは言われても、では、そのようにと、できないのが我々凡夫だ。
だから、不幸は儲かるよ、幸福はすり減るよ、と因果論を腹に落とし込み、苦楽を等価に観る捨の心を養うのだ。
業の結果に一喜一憂する世界に飽きれば、悟りたくなるだろう……。
2025年10月号
(1)
★暮れも正月も、人間が妄想を共有しているだけで、法として存在している訳ではない。
時ならぬ梵鐘の音に八王子の裏山の狸が目を開いたかもしれないが、『除夜の鐘か・・』とは思わない。
「音」とサティを入れた人間に近いだろう。
宇宙にはいつだって、ただの事実が存在しているだけなのだ。
事実に苦しむのは致し方ないが、誤った認知と勝手な妄想で苦しむのは愚かしい。
法と概念を仕分け、あるがままに観る瞑想を修行する所以……。
……………………
(2)
★早稲田に所用があったついでに、近くの母校を50年ぶりに再訪した。
文学部は激変していたが、大隈侯の銅像と時計台は往時のままだった。
受験の下見に初めて訪れた高3の冬の夕方、真っ赤な夕陽を背景に、黒々と浮かび上がった銅像のシルエットが鮮烈に心に焼き付いた。
そのイメージが、瞑想に人生を捧げる発端になるとは知る由もなかった……。
……………………
(3)
★妄想する能力を得た人類は、甘く美しい未来を夢見ることによって、苦しい現実に耐え抜こうとしたのだろう。
美しい夕陽の大隈候銅像は、受験勉強のヤル気に火を点け、合格に導いてくれた。
そして入学後に、夢と現実のギャップに打ちのめされ、苦と渇愛の構造を学んでいく発端となった……。
……………………
(4)
★未来の夢だけではない。
失恋の痛手も、出産の激痛も、どんなに苦しかった記憶も、やがて風化し、美化されていく。
記憶を書き換え、甘美な未来を夢想させ、苦しい現実を誤認させる妄想が充満した人類の脳。
果てしない輪廻の流れを永遠に続けさせる無明の力……。
……………………
(5)
★徴兵令が布かれた明治22年、徴兵忌避者がなんと9割以上。
「日本」や「国家」という妄想に殉じて死ねる民はわずか数%だった。
だが、共同幻想を徹底教育して半世紀、特攻隊の若者が機体もろとも次々と自爆していった。
妄想に生き、妄想に死す人類……。
2025年9月号
(1)
★速歩の歩行瞑想をしながら夜道を歩いていると、突然高笑いが耳に入り、反射的に「聴覚」とサティが入った。
自分が嘲笑されたのか…という印象が形成されかけたが、強引に断ち切られたと感じた。
ラベリングの言葉は概念だが、それ故に、心に生じようとする概念を消し去る「対消滅」の威力がある……。
……………………
(2)
★ヴィパッサナー瞑想は、エゴの妄想に毒された人類のための技法である。
事実をありのままに知覚するだけなら、ゴキブリも金魚も普通にやっている。
妄想を排除して知覚した瞬間、どのようにラベリングされ認識されるかが問題だ。
ガチャン!
「音」か、「(割れた)イメージ」か、「驚いた」か……。
……………………
(3)
★ラベリングなしのサティでも、現在の瞬間に気づくことができる。
一瞬でも言語脳を使うと、集中を高める仕事がやりづらいと感じる人も少なくない。
身体感覚への気づきはそれでも良いが、微妙な心の動きや意識の流れになると、ラベリング無しのサティでは認知が曖昧になり洞察智が生じにくい……。
……………………
(4)
★法としての事象がありのままに知覚されても、ゴキブリに悟りの智慧は生じない。
危険か餌かに機械的に反応する単純なプログラムでは、事象の本質が洞察されることも、煩悩が全捨てされる衝撃の体験にもなり得ないからだ。
一瞬の経験が、どう認識されたか…。
同じ音、同じ匂いを感じた瞬間、凡夫のラベリングと聖者のラベリングが同じだろうとは思えない……。
……………………
(5)
★認識が確定すると、心は次の瞬間に注意を向ける。
ガチャン!
① 中心対象の感覚に戻るのか、②花瓶を壊した連想に反応するか、③驚いた自分に違和感を持つのか。
一瞬の経験とその認識が、次の瞬間の反応に影響を及ぼす構造……。
……………………
(6)
★瞑想対象に集中しようと必死になっていると、なぜか力んでいる自分の姿が俯瞰され、ハッと我に返ることがある。
サティが本来の機能を取り戻した瞬間だ。
集中にこだわり、ガチガチだった全身からフッと力が脱け、やわらかく緩んでいく。
この脱力の瞬間を「軽安(きょうあん)」という…。
……………………
(7)
★歴史を学び、夢と希望に向かう人もいるし、トラウマに苦しみ、将来不安の妄想で自滅する人もいる。
想像力を持たないチンパンジーは、「今、ここ」だけに心を使いきり、過去を恨まず、未来に絶望することもない。
妄想を止め、サルの脳で経験し、ヒトの脳でラベリングするヴィパッサナー瞑想……。
2025年8月号
(1)
★日が暮れかかった頃、近隣の沼の畔を散策した。
何の変哲もない水面が夕陽に照り映え、異様な輝きを帯びて、刻一刻と化けていく…。
あるがままの法としての存在は見がたく、脳内フェイクの印象に執着し、最期までダマされ、空(す)かされ、誑(たぶら)かされながら、また死んでいくのか……。
……………………
(2)
★肉眼で見た世界は、写真のようなフレームも構図も何もない空間の拡がりに過ぎない。
視覚を最初に直撃したものが、「乱反射する夕陽」「湖面にさざ波を刻んでいく風」と認識された瞬間、概念化されてしまう。
写真の美しい色や輝きが一度心に焼き付くと、事実は消え失せフェイクしか残らない……。
……………………
(3)
★自分が何をやってきたのか、何を話し、どんなことを考えてきたのか、自分の人生そのものだった経験事象が朧(おぼろ)になり、やがて忘れ去られていく…。
のみならず、心に焼き付いたはずの記憶が修正され、リメイクされ、事実とかけ離れた妄想のドラマに変容し、エゴの脳内劇場で再演されていないか……。
……………………
(4)
★大嫌いな人、かけがえのない家族、無二の親友…がいるのだろうか激怒したり、安らぎを覚えたり、癒された一瞬一瞬に作られた過去の業が、その日その瞬間の経験事象として帰結しているだけではないか。
揺るぎない絆や犬猿の仲があるのではない。
業が生滅する束の間の事象の流れがあるだけということ……。
……………………
(5)
★真実であってもフェイクであっても、過ぎ去ってしまえば夢のようだ。
信頼の絆で結ばれていた掛けがえのない人も死に、毒々しい嫌悪の念を向けてきた人も死んだ。
愛も信頼も尊敬も嫌悪も軽蔑も…事実が歪曲されて編集されたエゴの脳内劇場。
もう猿芝居を止めたいのだが、幕が下せず立ち尽くす日々……。
……………………
(6)
★自分がこれまでに犯してきた罪業の数々、激怒した瞬間、暗愚な思考…その全てが形成した業を思えば、地獄行きだろう。
心から人のために力を尽し祈りを捧げ、寺に布施をし、懸命に瞑想した一瞬一瞬の業は、天界への再生に通じるかもしれない。
地獄も、餓鬼も、畜生も、修羅も、人間も、天も…、もう、因果に縛られた業の世界は、うんざりだ……。
……………………
(7)
★苦受を受け楽受を感じているのはこの「私」だ…という印象は、エゴ妄想に過ぎない。
なるほど、「私」が苦しいのではなく、苦の事実があるだけか。
でも…、だから、どうだというのだ。
業の結果を受けた瞬間、否応なく反応して新たな業を作り続ける輪廻の流れを、これからも永遠に続けるのか……。
2025年7月号
(1)本気で強いチェータナー(意志)を発し続ければ、いつか必ず現象化し具現化していくのが業の世界だ。
願望が引き寄せられるように実現するのも、同じ業の法則に則っている。
諦めた瞬間、ネガティブな結果を強く願ったかのように、そうなっていく……。
(2)膝を傷めた時、医者からもリハビリ療法士からも「もう治ることはない」と絶望を宣告された。
だが今や、1時間の座る瞑想が難なくできるようになった。
心の力が全てを創り出していく、と一貫して説いてきた。
限られた知識と経験で組み立てられた世界の暗示になどかかる訳がないという自負……。
(3)エゴや自我が法として実在するなら、仏教は無我論を説かなかっただろう。
ありのままの自分と、勝手に妄想している自己イメージとの間には、越えがたい溝がある。
真実の状態を否定し、抑圧し、次々と人生苦を生み出すエゴという偽の印象。
芋づる式に続くプライドと劣等感と渇愛……。
(4)劣等感が強く、しかもプライドも高い人は、ありのままの自分を観るサティの瞑想はやりたがらない。
化けの皮が剥がされ、イメージが崩れてしまう。
できない自分、カッコ悪い自分の真の姿を認める瞑想など、イヤや。
偉大なもの、崇高なもの、永遠なものとの合一を目指す方が好きやねん!
(5)妄想から執着が生まれ、執着から苦しみが生まれる。
そんなことは頭ではわかってはいるが、のたうつようにまた苦しんでしまうのは、思考モードを離れないからだ。
思考を止める訓練 、概念ワールドを出る瞑想が救いとなる。
「……と思った」と思考を対象化していく解放への道。
(6)写真記憶の能力を捨て、知覚情報を意味化する左脳を進化させた人類。
言語野を一瞬停止させて思考を止め、直接知覚した情報を再び左脳のスイッチを入れて認識確定するヴィパッサナー瞑想。
そんな脳の使い方を進化させていく人達は、共同幻想を信仰する人達と別の道を歩むことになるのだろうか。
(7)サティの一瞬に、全てがある。
好ましい対象に夢中になって、食いついてはいけない。
ネガティブな対象でも、ありのままに認めなければならない。
事の本質を洞察する智慧を得なければならない。
公平なエゴレスの視座から気づきを入れなければならない。
貪瞋痴から出離する一瞬……。
2025年6月号
(1)人は、なぜ瞑想するのだろうか?
なぜ瞑想は、孤独になって、森の中で、樹の下で、廃屋で、自分と向き合うのだろうか?
・・・瞑想会へ行ってみるか。
(2)欲しかったものが手に入り、欲望が満たされたときの幸福感。
人のお役に立つことができた。
人に心から喜んでもらえた。
あなたのお陰です、と感謝されたときの幸福感。
ゲットする幸せがあり、与える幸せがある。
成熟するということ・・・。
(3)合宿の最後は、沈黙行から解放された瞑想者が、簡単な自己紹介をしながら互いに親睦を深め合う。
ご家族を喪って瞑想に出会うまでの経緯が淡々と語られ、感銘を受けたこともある。
なぜ、これほどの悲しみを、かくも静かに伝えられるのか。
客観的な事実のみが呈示され、叙情が抑制されているゆえに、語り手の胸中への共感が深まり、心を打たれた・・・。
(4)修行が始まるや一斉に沈黙行が布かれ、誰もがサティの瞑想に没頭していく。
一日のどこかで必ず慈悲の瞑想をするのも義務化されている。
参加者全員が、他の全員に対して慈悲のバイブレーションを互いに放射し合っている状態。
一言もしゃべらず目も合わさず挨拶もしないのに、優しい沈黙が響いているグリーンヒル合宿の瞑想空間・・・。
(5)自信が持てない人、自己評価が低すぎる人、「慢」の煩悩に悩まされている人、正確な自己イメージが捉えきれない人たち・・。
エゴ感覚を手放し、因果の流れに我が身をゆだねきった人もいる。
いつでもどの瞬間にも、諸力に支えられ理法に貫かれた一挙手一投足・・と心得た人の静かな自信。
(6)子供の前で、夫婦喧嘩するほど、愚かなことはない。
子供の心を傷つけ、親が嫌いになる理由の1番か、2番・・。
(7)ともかく、そういうことが、起きてしまったのだ。
受け容れる覚悟を定めれば、経験の意味が変わり始める。
知識も経験知もあらゆる情報が、決意した方向に向かって結晶していく・・・。
2025年5月号
(1)汗とホコリで体が汚れるので、毎日お風呂に入る。
欲望と怒りと嫉妬と高慢で心が汚れるので、毎日瞑想をする・・・。
(2)ダンマの世界に心が洗われても、世俗の煩悩世界に戻ればたちまち泥んこになってしまう在家の悲しさ・・・。
(3)全てを押し流していく濁流のように、現象世界は生滅し流転していく。
善くも悪くも、情況は、変わっていく・・。
鋭いサティの入った正確な認識も、たちまち角が取れ、細部が誇張され、ステレオタイプの絵になっていく。
更新されていく色法と名法の世界、その一瞬一瞬に気づき続ける瞑想・・。
(4)同じ一つの現実なのに、100人いれば100通りの世界が脳内に拡がっていく。
何度見ても何百回聞いても、同じ理解、パターン化された解釈が自動的に立ち上がってしまう。
スルーしたものは常にスルーされ、人は見たいものを見ているだけだ。
・・・目からウロコが落ちるサティ!
(5)誤解と錯覚だらけの、デタラメの認識で人を恨み、狂おしく恋い焦がれてきたのではないか。
そんな、これまでの人生は何だったのだろう・・。
なぜ古来から「人生は一場の夢に過ぎない」と言われてきたのか・・・。
(6)瞑想しても手応えがなく、これといった結果が出ない・・・。
ものごとの真実の状態をあるがままに観ていく技法なのに、不正確なやり方で、いい加減にやっていないだろうか。
正確に実践すれば、システム本来の姿が露わになり、十全に機能が発揮されるだろう。
(7)生存のために進化してきた人類の脳・・。
地球の自然環境を破壊し尽くす勢いで、人工的に都市化させ文明化してきた結果、人の脳の使い方もいちじるしく変化した。
いつから人類は瞑想をしてきたのか、確かなことは分からないが、今ほど瞑想が必要な時代はない・・・。
2025年4月号
(1)赤裸々な感情を露わにするのが憚られる場面ではサティを入れ、冷静に、淡々と振る舞えたら素晴らしい。悲しみに浸りたい時には敢えてサティを入れず、心おきなく泣けばよい。自分自身を自在にコントロールし、なすべきことをなしていく。その拠りどころとなるヴィパッサナー瞑想……。
(2)……と、達観している人のサティ。いつ終わるともなく浮上してくる心の現象に「欲」「落胆」「失望」とラベリングしながら、際限なく一時停止をかけ続けるサティ……。
(3)世間では運命と呼ばれる「宿業(過去世のカルマ)」によって、人生の流れも寿命もおおむね決まっている。今この瞬間の意志が新たな業を作り、その流れを微妙に変えていく。調整はできるが、ほぼ決定された人生……。
(4)人格がととのい、反応系の心の汚染がなくなり、思考を止め判断を停止して、ただ一瞬一瞬の事象をありのままに受け容れていく……。
(5)同じエネルギーを出力をしても、対価の全額をもらえる人と、借金が天引きされてしまう人がいる。願いを叶える人も、努力の報われない人もいるのが業の世界だ。我が身に起きた事柄を、苦は苦のままに楽は楽のままに、ことごとく受け容れて感謝を捧げ、業の世界からの出離を目指す人達……。
(6)瞑想は、孤独ないとなみである。樹の下で、洞窟で、廃屋で、自分自身と向き合わなければならない。人と群れていてはならない。おしゃべりをしていてはならない。だが、人は独りでは生きていけないのだ。瞑想と孤独……。
(7)もう後戻りしない、揺るぎない反応系の心が確立されるまでは、自転車のペダルを踏み続けて坂道を上っていくと覚悟する。
2024年10月号
(1)若い頃、毎日、宇宙と一体になる瞑想に耽っていた。
宇宙の全てと一つになると、あらゆるものが自分のものという印象も生じた。
当然、地球も日本もこの東京の界隈も私であり、私のものだという錯覚を楽しんだ。
金はなかったが富裕感に満たされ、変哲もない日々が、妄想で輝いていた……。
(2)災害に見舞われたり、大きな苦難が訪れると、ハッと我に返り、ただ普通に暮らせていることのありがたさが身に沁みる。
夢や目標に向かっていく努力も、向上心も、悪いことではない。
だが、淡々と過ぎていく今日が、今の瞬間が、ツマラナイ駄目なものと見なされていないか……。
サティを!
(3)物作りも芸術もどんな創造や創作も、その技が極められていった果てには、ただ創造されたものだけが存在し、表現者のエゴが感じられない神業のような印象になるだろう。
「創造している私」「表現しているこの自分」というエゴ妄想が微塵も入らないからだろう。
「サティを入れている私」という感覚を微かに持ちながら瞑想している人には、頂門の一針である。
(4)日々の瞑想とダンマの学びによって、エゴが納得すれば、表層の心は変わるだろう。
ディープな瞑想や心底から揺さぶられる衝撃の体験があると、第2層の心も変わり、土壇場での反応にも矛盾がなくなってくる。
過去世から持ち越した性根のような第3層の心を、どこまで変えていけるだろうか……。
(5)下等哺乳類や鳥のように、丸ごと正確に覚えてしまう「写真記憶」の能力。
人類はそれを捨てた替わりに、記憶情報をバラバラに並列保存し、概念化したり全体から本質を抽象する能力を得た。
事実を正しく観るサティの瞑想と、ダンマに基づいた情報の編集で、人生は一変する……。
(6)経験した出来事が問題なのではない。
どのように脳内再生を繰り返すか、だ。
ムカつく言動に絞り込んだ恨み篇。
感謝のフィルターをかけてつなぎ合わせた感動篇。
断片化された記憶が編集された脳内物語……。
(7)迷えば、ブレれば、ためらえば、正と反、肯定と否定の意志を交互に、あるいはデタラメに放つことになる。
やるのかやらないのか、行くのか戻るのか、壊すのか創るのか、自分が放ったエネルギーを自分が相殺している愚かさ。
諦めれば、起きない。
願い続ければ、いつか必ずそうなる……。
(8)日暮里の路地に入った瞬間、ゴキブリを目撃した。
踏まれたのか、飛び出した体液で路面に貼りつき、虚しく手足を動かしていた。
死んでいこうとうしている命のはかなさに心が傾き、嫌悪感が微塵も生じなかった。
「目撃」→「情況の認知」→「憐れさ」と反応した心。
2024年9月号
(1) 歩くことは、極めて高度な脳の働きによって支えられている。
ギリシアの賢者達が歩きながら哲学していたのも、脳科学的に理に叶っていたようだ。
私も、原稿の筆が渋り、アイデアに行き詰まると、歩く瞑想をしながら近辺での所用を果たすことにしている。
ほぼ確実に閃きが得られている。
(2)この世の煩悩の対象であろうと、彼岸の超越的な対象であろうと、求めている執着の手を離さない限り、苦しみが生まれてくる。
執念で得たものも無残に壊滅していくのが業の世界だ。
ゲットしても、永遠の不満足性がくすぶる。
限りなく手放して、究極の引き算の果てに拡がる安息と静寂……。
(3)昔、まちがえて洗顔フォームを歯ブラシに塗り、口に入れた瞬間、ギャッと叫びたくなる違和感を覚えた。
「毒!」と判断せず、歯磨きの味も分からなくなった自分の味覚不全を責める意識が過ったことに感動した。
『何があっても、自分が悪い』と考える修行を必死でしていた時代だった……。
(4)「瞑想なんて、ただボーッとして、いい気持ちになってるだけだよ。あんなものやったって、どうもないわ」
では、一瞬一瞬の身体感覚を感じながら、サティを入れて歩く瞑想はいかがですか。
歩いている自分に気づいて、自分を対象化し客観視する練習です。
自己チューの視座の転換……。
(5)何も考えないだけなら、蛙やトンボや眠りこけている人と同じではないか。
なんとなくまぶたの裏をボーッと眺めている鈍重な無思考状態では意味がない。
音や匂いや思考が浮かんだ一瞬の、リアルな現実に明敏に気づく意識の修練。
そこからだ、存在の本質を洞察する智慧が閃き出すのは…… 。
(6)サティを入れ、余計な妄想を排除していくと、思考から生まれる欲望と怒りから自由になれる。
何も持っていなくても、苦の種である妄想と執着を引き算していった果てには、ただありのままの自分で豊かに自己完結していることに気づく……。
2024年8月号
(1)我執が深くエゴが強い人の中でも、自分を嫌悪し怒りを持っているタイプの方は慈悲の瞑想がノラない、 上手くいかない、苦手だ……ということが多い。
対策は、怒りとエゴを引き算することだ。
他人を利する利他行や善行を課題にするとよい。
エゴ感覚を弱め、他人を思いやる練習……。
(2)反射的な衝動に従ってしまえば……、浮かんだことをそのまま言ってしまえば……、人は必ず愚かなことをしてしまう。
人格完成者でもなければ、悟りを開いたわけでもない凡夫が、自分のされてきたことを無意識に再現しながら子育てをしているのだ。
よく気をつけておれ、とブッダは言う。
(3)堂々めぐりになった思考回路では、何も書けず、途方に暮れるばかりだ。
歩く瞑想をすると、思考が止まり、頭の中を空っぽにできる。
余計な回路が閉じられれば、脳内の全データが使用可能の状態になる。
すると、意識下の必然性が必ず一瞬の閃きをうながしてくれる。
歩けば、智慧が出る……。
(4)歩くことは、極めて高度な脳の働きによって支えられている。
ギリシアの賢者達が歩きながら哲学していたのも、脳科学的に理に叶っていたようだ。
私も、原稿の筆が渋り、アイデアに行き詰まると、歩く瞑想をしながら近辺での所用を果たすことにしている。
ほぼ確実に閃きが得られている。
(5)この世の煩悩の対象であろうと、彼岸の超越的な対象であろうと、求めている執着の手を離さない限り、苦しみが生まれてくる。
執念で得たものも無残に壊滅していくのが業の世界だ。
ゲットしても、永遠の不満足性がくすぶる。
限りなく手放して、究極の引き算の果てに拡がる安息と静寂……。
(6)人生に迷い、道を求めて東に西に遍歴しなければならなかった。
カルマが悪かったのだろうか。
その結果、デタラメな情報やネガティブな経験を重ね、膨大にデータ化されていった。
それは、瞑想ができない人を教える上での宝物になった。
カルマが良かったのか、悪かったのか……。
(7)因果関係がしっかりしていれば、どんなことでもあり得るのが業の世界だ。
成功の瞬間がある。
失敗の瞬間がある。
ただその状態が一瞬あっただけなのに、心の中に焼き付いた「静止画」が苦の元凶となる。
事実を握り締めることはできない……。
2024年5月号
(1)心は多層構造である。
表面意識が無思考状態に入れても、意識下で通奏低音のように鳴り響いているものがある。
トラウマや劣等感などが多いが、それだけではない。
慈悲の瞑想に集中してからサティの瞑想を開始すると、暗黙の慈悲の波動が放たれる。
優しい空間が出現する所以である。
(2)瞑想は、孤独な営みである。
外界の人や環境との関わりを一時的に中断するからである。
腐った内面を浄化し整えるためには、まず独りになって情報の乱入を拒み、思考や判断を停止しなければならない。
瞑想者は内閉的な世界に自らを閉ざすがゆえに、ワガママになり独善的になる危険がある。
(3)余計な妄想を駆逐するサティの持続と、互いに思いやりさりげなく配慮し合う慈悲の瞑想の波動が絶妙にハーモニーを奏で、瞑想道場は優しい沈黙に包まれていく……。
(4)それだけではない。
人にも情報にも環境にも恵まれなければならない。
外的な条件は、これまでに作ってきた善業と不善業によって決まる。
徳がなければ瞑想が進まない所以である。
そして全てが整っても、心に傷がありわだかまるものがあれば、瞑想は破綻する。
反応系の心を組み換えていかなければならない。
(5)苦楽中道の原始仏教では、断食は苦行と見なされるのが常識である。
しかし2日程度の断食は苦行ではなく、体の毒素を排除するデトックスであり、瞑想を深める技法である。
秀逸な瞑想は意識の透明度に比例し、意識は体調、体調は食事の調整によって決まる……。
(6)自分に対する怒りであれ、他人への憤りであれ、怒りは対象を打ち消し、拒み、否定し、破壊するエネルギーである。
怒りを発すれば、その被害を最も深く、強力に受けるのは、自分自身である。
病む。怪我をする。心が傷つく。関係が壊れ、情況が悪くなる……。
愚か者は、よく怒る……。
2024年4月号
(1)自分が犯してきた悪業の相殺のために、人を押しのけるように強引な善行をしている人もいる。
皮算用どおりの報果が得られなければ、取引で損をした人のように怒り出すにちがいない。
本当の優しさも、真の善行も、「私が幸せでありますように」を成就した人からこぼれ落ちる……。
(2)素晴らしい善行をしているように見えるが、ああ、この人は自分の徳のポイントを増やす事しか考えていないのだな……と、分かってしまう人がいる。
エゴイストの冷たい優しさ……。
(3)自分からは何事も決めることなく、ただ、必然の力で生起してくることをそのまま受け容れていく生き方をしてきた。
嫌だな……と反射的に、ネガティブな反応が立ち上がることも多々あったが、我執の判断が入らない仕掛けになっていた。
受動性に徹した生き方をしていくと、宿業に組み込まれていたものが顕わになっていく……。
(4)何事も、最初から正師につけばよいものを、回り道しながら遍歴することが多かった。
失敗を重ね、試行錯誤を繰り返す必要があったのだろうか。
後年、自ら望んだ訳ではない不思議な展開で、瞑想指導にたずさわると、バラバラにやり散らかした全てが必要な学びだったとリンクしてきた……。
(5)ついに究極の道にたどり着いた確信が込み上がってきた原始仏教だった。
だが、分け入ってみると、同じ原理と基盤の上に立ちながら、修行現場では微妙に異なるいくつもの技法が行じられていた。
経験知と直観を拠りどころに、さらに求法の旅を続けた果てに、異国の森林僧院に導かれていった……。
(6)私が初めてヴィパッサナー瞑想を試みた20数年前は、寺も文献も師もインターネットも、情報というものがほとんど無かった。
既存の脳内データを全開にして、闇の中を手探りで試行錯誤していった。
正解が封印されていたがゆえに、瞑想の構造的理解が深まり宝となった。
2024年3月号
(1)眼鏡の汚れを拭けば拭くほど、顕微鏡の倍率を上げれば上げるほど、微細なものまで鮮明に見えてくる。
心がきれいになればなるほど、自分の心の汚さ、未熟さが見えてくる。
心が真っ黒な人ほど、自惚れる……。
(2)煩悩に汚れた心を自覚しても、浄らかになりたいと願っても、怒ってしまうし、妬んでしまうし、貪ってしまう……。
溜め息をつきたくなるが、心の成長というものは、ゆるやかに、しずしずと進行していくものだ。
上手くいかないから練習があり、修行がある。
心は、必ず変わっていく……。
(3)完全に不要になったゴミを捨てる瞬間に、怒りはない。
執着が何もない「手放し」の感覚が、仏教の引き算だ。
獲得すれば獲得するほど、束縛と苦しみとエゴ感覚が肥大していくことに気づかない無明。
足し算の貧しさ、引き算の豊かさ……。
(4)「よーし、いいこと聞いた、やってみよう」と、猿真似をすると上手くいかないものだ。
期待と欲でワクワク、ギラギラしている人には、無心に行なった人の「捨」の心がない。
ビギナーズラックが起きるときの要因の一つだろう。
余計なことは何も考えず、「一所懸命、淡々と」できますか?
(5)ヴィパッサナー瞑想を実践して2ヶ月だが、3つの効果があったという。
①仕事が速くなった。
②クレーマーに怒鳴られる業種なのに、自分だけ激減。
③苦手な上司と理解し合えるようになった。
①はサティの効果。②は慈悲の瞑想。③は①②の相乗効果で自己中心的な見方が変化したから、と解釈される。
(6)壊れた水道のように、四六時中思考が止まらないのが人の基本設定だ。
集中し、サティを入れ、思考の止まった静かさを味わう。
さらに、後悔を、自責の念を、恨みを、抑圧された闇を手放すと、心はいちだんと静かになる。
雑念のない清潔、深層の心も浄らかにした自信と安息、深められる瞑想……。
2024年2月号
(1)夜道を歩いていたら、角の暗がりから突然「福は内!」と大きな声がした。
そして、「鬼は外!」のタイミングでこちらに向かってパラパラと豆が飛んできた。
幸福は我が家だけに、災いの元凶は他所に……という訳か。
嫌いな人や敵対する人にすら「幸せであれ」と祈る瞑想との落差を感じた。
(2)晴れた日は楽しく、風の日は全てがクッキリ明晰だ。
雨の日は肌も潤い、葉群の緑も樹皮も美しい。
淡い曇りの日は心が落ち着き大好きだ。
雪が降る。現実が詩的になる。
冒険好きなので嵐が来るとワクワクする……。
全てを肯定できれば、現象世界が達観される。
執着がなくなると、苦が激減する……。
(3)狼がきたぞ!という誤情報からでも、現実の反応が起き、大騒ぎになってしまう。
そのように、実体のない幻のような「エゴ」であっても、傷ついたという印象を受ければ、ホルモン系に一連の反応が起き、愛着障害のような問題も発生してしまう。
「自我」を確立してから「無我」を悟る順番……。
(4)「愛するものから憂いが生じ、愛するものから恐れが生ずる。愛するものを離れたならば、憂いは存在しない」とブッダは言う。
「安全基地」を体験した者は、「安全基地」を手放すことができる。
万物と繋がり合い万物に支えられていると知り、無我を体得した者は、独り犀の角のように歩む……。
(5)自信がなく、自己嫌悪や自己否定感覚との葛藤で苦しんでいる人たち。
そんな自分を丸ごと受け容れてくれる揺るぎない絆に支えられれば、安心してのびのびと実力を発揮できるだろう。
だが、その支えを失えば、絶望的な悲しみの中に失速する。
何ものにも依存しない自己完結を目指す……。
(6)歩く瞑想のやり方が間違っていたわけではなかった。
だが、インストラクションを受け、ひとつ一つの動作に溜めを作ってから感覚を取り、余韻を感じてからラベリングをするように微調整した。
すると、頭の中が異様なほどクリアーになったという。
自覚されない妄想の微塵まで一掃された世界……。
2024年1月号
(1)外国で一度だけ出会った僧の言葉が、その後の人生の指針となったこともある。
20年以上瞑想会を続けてきたが、事実上、一期一会となる方が多い。
それゆえに、なんとかヴィパッサナー瞑想の本質を伝えたいと、その一瞬に集中してきた……。
(2)夜道を歩いていたら、角の暗がりから突然「福は内!」と大きな声がした。
そして、「鬼は外!」のタイミングでこちらに向かってパラパラと豆が飛んできた。
幸福は我が家だけに、災いの元凶は他所に……という訳か。
嫌いな人や敵対する人にすら「幸せであれ」と祈る瞑想との落差を感じた。
(3)自らを拠りどころとし法を拠りどころとするには、どうしたらよいのだろうか。
ブッダは言う。
「よく気をつけて身を随観し、受を随観し、心を随観し、諸々の事象を随観して、貪欲と憂いとを除け」
つまり、ダンマが自らに顕わになるとは、サティの瞑想をしている一瞬一瞬だということ。
(4)「自らを頼りとし、他人を頼りとするな。法(ダンマ)を拠りどころとし、他のものを拠りどころとするな」とブッダは言う。
本能の命じる声ではなく、なんの根拠もない自己肯定感でもなく、ダンマが顕わになった自分を信じる力が本当の「自信」だということ……。
(5)ギラギラしたエゴ感覚と煩悩に満ち満ちた自分を信じるのが「自信」なのだろうか。
それは愚か者の我執に過ぎない。
理法(ダンマ)に基づいて生きていく覚悟が定まった自分に揺るぎない信頼を定めていく。
「自信」とはそういうことである。
(6)持てる力を全てやるべきタスクに投入できたら、素晴らしい結果が花開くだろう。
自信がない人の心の中では、「やれるだろうか」「大丈夫だろうか」と不安との戦いや、内面の葛藤にムダなエネルギーが費されヘトヘトになっていく。
「信(サッダー)」のない人は、自滅していく……。
2023年12月号
(1)これは、手のかかる、厄介な人だな、と溜息を吐きたくなるような修行者もいる。
だが、例外なく、そんな苦労したインストラクションを通して、最も深い学びを得ることになる。
善きにつけ悪しきにつけ、出力したエネルギーに比例した甘美な果実、もしくは苦い果実を刈り取らされる法則だ……。
(2)「なぜ私は、サティの瞑想が続かないのでしょうか?」
「この世のことに囚われているからです」
「私は、この世を捨てたいと思ってます」
「それなら、思考にサティを入れ、見送りなさい。
思考の中身は全てこの世のことです。
概念の世界を世間と言います。
あなたは、世間が大好きなのです」
(3)どのような苦しみも、脳内に固着した「渇愛」という名の執着が手放されれば、終わるだろう。
望みのものが手に入り、報復に成功し、「夢が叶う」場合もある。
諸般の事情と因縁の流れを見て、「妄執だった……」と静かに諦める場合もある……。
(4)嫌なものがイヤではなくなっていくプロセスが、心の成長である。
お膳を引っくり返す。
斬り捨てる。
戦争を始める……。
ストレートに怒りを露わにするのは、幼稚なことだ。
環境ではなく、認知を変え、心を変え、生き方を変えていく……。
(5)「この世のことなんて、どうでもいい。私は悟りにしか興味がありません」
「あなたが求めているのは、思考で考えた悟りです」
「嘘です。 私は本当に悟りたいのです」
「それなら概念の世界を一切捨てなさい。本気でこの世から出離する覚悟があれば、妄想は止まるでしょう……」
(6)諸法無我の対極にあるのは、我を張り、私が俺がと自慢し、差別し、人を見下す、エゴイズムの世界だ。
駆け巡る思考、多発する妄想、荒ぶる心、昂り、暴れまわる心……。
その興奮と混乱が静まり、心に沈黙が拡がっていくと、見えてくる存在の本質、この世界の真相……。
瞑想しよう……
2023年11月号
(1)意識的なことよりも、なんとなく感じていることや無意識に思っていることの方が強く出力され、業を作っていくものだ。
無自覚な思考パターンに、気をつけなければならない。
無くて七癖の常同的振る舞いの自覚化から、人生の流れが変わっていく……。
気づきの瞑想をする。
サティを入れる……。
(2)過去に作った善業や不善業によって、日々経験する事象はほぼ定まっている。
最悪の事態も超ラッキーなことも、起きることは決定的に起きてしまうのだ。
それに逆らう自由も、受け容れる自由もある。
古い業が新しい業によって微調整されていく瞬間だ。
サティを入れて見送るという選択……。
(3)日常生活では、顕微鏡モードの厳密なサティから肉眼モードに変換しなければならない。
眼耳鼻舌身意の情報の中身を理解しながら、「見ている」「聞いている」「考えている」と自分を俯瞰していくのだ。
今、自分は何をしているのかに気づこうとすればよい。
自覚の維持を心がけるマインドフルネス……。
(4)次々と水面に拡がっていく波紋のように、優しさから優しさが手渡され伝えられていく。
だが、愚かな善意と智慧なき優しさは、人を真の幸福にみちびかない。
現状を正確に把握し、何が本当に相手のためになるのか熟慮されるべきではないか。
明晰な智慧と優しさが連動する慈しみの瞑想……。
(5)1年後には、記憶の40%は当てにならなくなり、感情の記憶になると60%は食い違ってしまうという。
そもそも今の瞬間をあるがままに見ることが至難の業なのに、その不正確な記憶がさらに変容してしまうのだ。
生きてきた証しは記憶しかないのに……、人生とは、何なのだろう。
(6)思考の流れが止まり、静かになった心の内奥に耳を澄ませ、どうしてもやりたいと感じることはやってみるしかないだろう。
痛い思いをしなければ骨身に沁みないし、失ってみて初めて値打ちに気づくものだ。
学ぶべきことを学ぶなら、自ら蒔いた種を刈り取る苦しい人生にも意味がある……。
(7)何のデータも入れなければ、優秀な演算機能を持つパソコンも空箱同然になってしまう。
学ばない、考察しない、情報を集めない、練習もしないし、修行もしない。
ただ心を空っぽにして、静かにしているだけで洞察の智慧が閃くだろうか。
現実逃避の瞑想、虚しい空っぽ、無意味な静けさ……。
(8)習練すべき技能が修められ、必要な情報が十分に集められているならば、余計な準備や計画で頭をいっぱいにしない方がよい。
その瞬間、即興で閃くものにはムダがない。
脳内に用意されたものを意識的に具現化するタスクは、今の瞬間にブレーキをかけるだろう。
心を空っぽにして、静かにしていること……。
2023年9月号
(1)崇高な心も、醜い心も、煩悩に目が眩むのも、智慧が閃く刹那も、どの一瞬も真実だったのだ。
強引にまとめ上げた「自己イメージ」に執着すると、人生が苦しくなる。
他人のイメージも一つに要約し、まとめてはならない。
存在は一瞬の現象の連鎖であり、前後際断、個々別々と心得る……。
(2)一瞬の意志が、グラリと人生の流れを変えていく。
その意志は、どのように定められていくのか。
人の心は、どう変わっていくのだろうか。
(3)瞬間的にエゴ感覚が弱まったときに、自己客観視の任務を担ったサティが入るのだろうか。
瞑想修行の結果、サティの脳回路が自動化されてきたがゆえに、エゴの独裁支配を客観視する瞬間が訪れるのだろうか……。
(4)集合された無数の情報と要因が、必然の力で一つの反応を立ち上げる。
反射的かつ自動的なプロセスで一気に心のドミノを倒していくが、熱心にサティの瞑想をした者には、客観的に情況を把握する一瞬が訪れるだろう。
そのまま殴り倒す自由もあるが、上げた拳を下ろす自由もある。
闇も、光も……。
(5)何でも自分で考え、選び、自分の意志で決めていると錯覚している人が多い。
だが、自分の意志がはたらいた瞬間、その0.5秒前には既に脳の活動が始まってい ることを脳科学は明らかにしている。
自由意志とは、脳が膨大な情報処理をした最終結論を、ただ宣告するだけの役割で はないのか……。
(6)末端の現場の情報が経営方針を左右するように、中枢は末端の奴隷に過ぎないかもしれない。
一瞬の意志を決定しているのは「自分」ではなく、周囲の環境の情報と過去の経験、知識、親の影響、劣等感、トラウマ、長年の夢……等々、膨大な要因と諸力がはたらいた結果ではないか。
無我とは……。
2023年8月号
(1)ネガティブな情況の流れを静かに受け止めているのか、否定的なものの見方と反応の結果を自ら具現化させているのか?
どうしようもない嫌なことに巻き込まれたのではなく、無意識に自分の望んだことが起きているのではないか。
悲観と負のスパイラルの中で、業が帰結し、新たな業が作られていることに無自覚な人……。
(2)チワワからセントバーナードまで、これだけ色も大きさも顔も形も異なるのに、同じ「犬」として一つにまとめてしまう。
その能力が、万物の中に無常の法則を洞察させるのだろう。
いつまでも昔のことを恨み、邪推し、将来不安に怯えながら暮らす、妄想の地獄も手に入れてしまったが……。
(3)人は、「理不尽」と感じた時と「自分が正しい」と思ったとき、最もよく怒る。
因果論を徹底的に理解すると、「起きたことは全て正しい」という意味が腹に落ち るだろう。
すると、怒りに気づいて抑止するのではなく、怒りという反応そのものが激減する。
愚か者は、よく怒る……。
(4)ツイッターの原稿を書こうとタブレットに触れた瞬間、いきなり操作不能となり アッという間に初期化されてしまった。
再使用可能となるまでの煩わしさを思い、一瞬、呆然としたが、冷静だった。
時間を空費する不善業が現象化したのだろう。
腹が括れていれば、嫌悪も失望もあり得ない。
(5)聖者でない限り、不善業を作ってしまう瞬間も悪意が浮かぶ一瞬も、悲しいかな、 無くすことができない……。
人生苦を受ける原因をゼロにはできないのだから、この世は一切皆苦の構造であり 続けるだろう。
のみならず、久遠の過去世からの負債はいかばかりか。
解脱するしかない……。
(6)なぜ、あの人に……と首をかしげたくなるような事に襲われるのが人生だ。
だが、現象が生起したからには、相応のカルマを作った瞬間があったはずである。
お釈迦様ですら、罵られたこともハメられたことも足指に棘を刺したこともあった のだ。
起きたことは全て、引き受けていく覚悟……。
2023年7月号
(1)劣等感が強い人ほど、人の恩を忘れていくものだ。
お世話になり、導いていただき、やっとここまで来られたのに、何もかも自分ひとりの力で成し遂げてきたかのように認知が変わってしまう。
屈辱の過去に復讐するかのように、傲慢な上から目線になっているのに気づかない……。
(2)言われたとおり丁寧に、セオリー通り修行するビギナーの初々しい姿に、タジタジとなる古参。
解ったつもりになったダンマは、何回耳にしても、ああ、あの話か……と同じ理解が右から左に素通りだ。
ボロボロになった座右の書から、果てしなく新たな意味を汲み取る智慧の人もいるのだが……。
(3)ハカライというものは、必ず破れていくものであり、いつか行き詰まっていくものだ。
仮に最後まで、人に知られることがなくても、作られていった業が噴き出て来る日がやって来る……。
(4)ああ、自分はひどいことをしている……と自覚しながら悪いことをする人は少ない。
これは良いことだ、当然のことだ、と思いながら、好きなこと、やりたいこと、信じていることをやっているのだ。
……こうして誰も、毎日、嫌な人に出会い、不快な出来事に苦しむ人生になっていく……。
(5)地獄の極悪人にすら、蜘蛛の糸が垂らされてきた。
本当は誰にでも、チャンスは訪れているのだ。
ぼんやり見送ってしまう人。
自ら断ち切ってしまう人。
紙一重で救い出される人……。
カルマが現象化するのを助ける支持業があり、邪魔をする妨害業がある……。
2023年6月号
(1)苦しい人生が劇的に変化する感動に支えられてもきたが、全てがバラ色の幸福の絵に塗り替わって永遠に続く……などということがあろう筈はない。
業があれば、苦の現実は苦のままである。
それゆえに、どんなドゥッカ(苦)も受け入れれば終わっていく…というダンマの確認が繰り返されていった。
苦楽も失敗も成功も、一切の事象を等価に観て、淡々と無差別平等にサティを入れていく瞑想を続けていくうちに、こんなことを述懐するようになっていた。
「何もうまくやる必要もなく、苦を避ける必要すらなく、ただ今という目の前にある物事に気づいて、力を出すことを惜しまずに、淡々となすべきことを成していくだけなのだと、美しい春の朝の道を歩きながら実感していました……」
(2)人は、今の瞬間の事実に苦しんでいるのではない。
消え去ってしまった現実は、もはや「過去」という名の妄想に過ぎない。
苦しみは、その「過去」にしがみつき、囚われ、執着する精神から発生してくる……。
それゆえに、聖者たちは、今のことだけで暮らしている……。
(3)瞑想を始めればすぐに華々しい成果が得られると勘違いするのは、多くの初心者の通弊と言えるだろう。
初めて瞑想会に来て、「上手くいきませんでした。どうしてですか?」と真顔で訊かれる方も珍しくない。
一度も触ったことのないピアノやヴァイオリンを初めて習った日に、「どうして上手くできないんですか?」と訊く人がいるだろうか?
何事も修練を繰り返すことによって、新しい脳回路が形成されていく。
定着させるのも容易ではないが、維持するのも、さらに進化させるのも大変なことである。
どんな技能もスポーツも演奏も瞑想も、同じなのだと心得る。
(4)だが、ヴィパッサナー瞑想に正しく着手しても、生来の資質や傾向が手のひらを返したように変わることはない。
急激な変化には反動があり、一時的な決意や戒めや外圧によって抑え込まれていたものは、やがて形状記憶合金のように元通りになっていく。
ヴィパッサナー瞑想に出会い、くらくらする程のカルチャーショックを受け、物の考え方も行動も生活も別人のように一変したのだが、1年経ち2年経ちするうちに次第に失速し、浮かない顔で惰性に従っていたある日、忽然と姿を消していくような人もいる。
ゆるやかに、少しづつ変化していくのが人の心である……。
2023年5月号
(1)苦しむだけの人生にも意味がある。
苦受を感じる一瞬一瞬、消えていく不善業のエネルギーがあるからだ。
(2)イヤだ、嫌だ、と言いながら、本当は、そのドゥッカ(苦)が好きなのではないか……。
(3)後になれば夢のようだと得心がいくのに、その渦中にいる時は、本気モードで反応しながらしっかり業を作ってしまう。
……どうすれば良いのか。
反応系の価値観や人生観が根底から変わるまでは、サティの技術に支えられていく……。
(4)苦受の多い日々であっても、楽受が多くても、この世のことはただそれだけのことであって、過ぎ去ってしまえば夢のようだ……。
(5)業の理論上、来るべきものは来るし、原因が組み込まれていないものは、発生しようがない。
エゴの判断基軸を捨て、理法に一切を託し、悠々と流れに従っていけばよい。
(6)この世の一切を捨てていくのが原始仏教の究極の方向だが、ものごとを手放してい くのには順番がある。
心が完全に納得了解した上で一つひとつトドメを刺していけば後戻りがない。
それゆえに自分の現状にありのままに気づいて、在るものは在る、無いものは無 い、今は無いが再び現れるものは現れる……と正しく知らなければならない。
(7)世界最大の魚ジンベエザメとゴキブリの赤ちゃんでは、体の大きさも食べるものも 棲む場所も寿命も違っているので、優劣を競ったり、 見下したり、嫉妬し合うのは 滑稽だろう。
そのように、人は誰も、長い輪廻の中で積み重ねてきたカルマと諸々の因縁因果が 異なるのだ。
エゴ妄想で強引にまとめれば、苦が発生する……。
2023年4月号
(1)他人を意識する。
不安を感じる。
緊張する。
・・・現在の瞬間にすべての注意を注ぎきることができれば、無心になれるのだが・・・。
(2)[尊師いわく、―]
「快く感ぜられる色かたち、音声、味、香り、触れられるもの、―これらに対するわたしの欲望は去ってしまった。そなたは打ち負かされたのだ。破滅をもたらす者よ。」(サンユッタニカーヤ1-4ー1-4)
(3)そのとき悪魔・悪しき者は尊師に近づいてから、尊師に向かって、詩を以って語りかけた。
―「かけ廻るこのこころは、虚空のうちにかけられたわなである。
そのわなによって、そなたを縛ってやろう。修行者よ。そなたはわたしから脱れることはできないであろう。」(サンユッタニカーヤ1-4ー1-3)
(4)六門に乱入してくる情報に刺激され、一瞬も止まることなく振動してしまう心・・・。
その究極のドゥッカ(苦)に追いつめられた心は、寂滅した静けさを目指す・・・。
(5)瞑想をしなければ、騒がしい心が苦であるという認識も生じないだろう。
想いが乱れ、心が乱れ、ネガティブな思考が心を駆けめぐって煩悩が生まれ、不善業が形成された結果、苦の現象に叩かれて苦受を感じる瞬間まで・・・。
(6)業の結果を受け取る心が一日中、落下する滝のように生滅を繰り返している・・・。
その心とワンセットになって、眼耳鼻舌身意の情報に反応しながら、業を作る心がたたき出されていくのも止まるところがない・・・。
「業の結果を受ける瞬間」→「業を作る瞬間」→「業の結果を受ける瞬間」→「業を作る瞬間」→・・・。
震え続け、反応し続ける心のシステムに圧倒され、翻弄され、拘束され続ける状態には、一瞬の自由もない。
安息もない。
静けさもない・・・。
(7)自信がなく、自己肯定感の乏しかった母親が、子供の卒業式にひとり涙した。
自分と同じ苦を受けないように、丁寧な愛情を注ぎ、全身全霊で子育てしてきた結果、 自己肯定感のある優しい子に成長し、一区切りが着いたのだ。
瞑想に出会いダンマを指針とし、揺るぎない決意があれば、苦は乗り超えられていく・・・。
(8)苦しい経験をしてきたがゆえに、人はダンマ(理法)に出会う・・・。
2023年3月号
(1)可愛い自分にも嫌な自分にも、法としての実体はなく、エゴ・イリュージョン(幻想)というか、「自我感」というただの印象に過ぎない。
サマーディとサティが高度なレベルで連動したヴィパッサナー瞑想が、その実状を目の当たりにする。
(2)本当は、誰よりも自分が可愛いし、自分さえ良ければよいと思っているのに、激しく自分を否定し、嫌悪する日々……。
(3)エゴ意識があるので、他と比べてしまう。
高慢になって、人を見くだす。
卑下慢になって、落ち込む。
劣等感を引きずれば、四六時中、何をしていてもネガティブ思考がチラチラと蒸し返され、意識の水底を引っかき回して濁らせる……。
集中が悪い。
サティが空振りする。
修行が進まない……。
(4)他人を意識した瞬間、比べる心が働いていただろう。
不安を感じた瞬間、心は未来に飛んでいたのだ。
緊張した瞬間、成功へのこだわりがあったのではないか。
余計なことを考えて集中が破れた分だけ、その瞬間のパフォーマンスが乱れる……。
(5)正しい技法と習得への情熱があれば、道を極めていくことができる。
ブレることなく専念するには、なぜ、そうするのか、自分はどう生きるべきなのか を心得ておかなければならない。
宿業や運命の押しやる力と自らの自由意志がきれいに重なった時、人は輝く。
まず、現状に気づくサティ!
(6)どの分野でも、名人の域に達した人の脳活動を調べると、ごく一部の脳領域しか使われていないという。
素人や初心者ほど、どこに、どう注意を注ぎ、何を、どうすればよいのかが分からず、力いっぱい余計なことをしてしまう。
なすべきことを正しくなすには、どうしたらよいのか……。
2023年2月号
(1)望むままに、自由に、奔放に、生きていく人生もある。
与えられた運命に、淡々と従いきっていく人生もある。
さしたる違いはない……。
(2)自然に放置すれば、全てのものが散らばって、混沌とした無秩序に向かっていこうとするのが存在の世界だ。
その基本的傾向に逆らい、有機的に結晶した秩序ある状態を維持しようとするのが生命活動である。
壊れていこうとする力に逆らい、抑制をしなければ、生きていくことはできない……。
(3)過食をすれば体が濁り、眼も耳も鼻も味覚も身体感覚も鈍重になり、すべてが物憂く、どんより、ボンヤリ、どうでもよいと投げやりになって、眠気に引きずり込まれていくのに抗う気にもなれない……。
坂道を転がり堕ち始めていく最初の無明……。
(4)食欲がきれいにコントロールできると、体がスッキリと整い、心も透明に澄みきって、瞑想のクオリティが格段によくなってくる。
「ああ、この状態を保っていきたい……」と誰もが望むのだが、必ず気がゆるんで、節度を失う瞬間が訪れる。
寄せては引き、引いては寄せながら徐々に潮が満ちてくるように、一直線の右肩上がりは、あり得ない。
(5)「膨らみ・縮み」とサティを入れ、「離れた→進んだ→着いた」とラベリングする。
技術的にサティを入れることはできても、エゴを対象化し、どこまで自己客観視が できているかは千差万別、ピンからキリまでの個人差がある。
心が本当に成熟し、人格が完成してくるのに比例して、エゴレス度が深まっていく……。
