比丘ボーディ
四聖諦(三)
―ニッバーナ(涅槃)―
「私が説くのは、ドゥッカ(苦)とドゥッカ(苦)の消滅についてだけである」とブッダは語っています。
第一の聖なる真理は苦の問題を扱っています。しかし、苦の真理はブッダの教えについての最終の言葉ではなく、出発点にすぎません。
ブッダは苦の教えから始めます。それは、ブッダの教えがある特定の目的、つまり苦からの解放へ至る道を目指しているからです。
この目的を達成するために、ブッダは解放を目指す理由を私たちに示す必要がありました。自分の家が火事だということを知らなければ、人は楽しんだり、遊んだり、笑ったりしながらその家に住み続けます。その人を火事の家から連れ出すには、まずはじめに家が火事だということを理解させなければなりません。同様に、ブッダは「私たちの人生は老病死で燃えている」と教えています。私たちの心は貪瞋痴で燃えているのです。その危険に気づかなければ、私たちは解放への道を求めようとはしません。
第二の聖なる真理により、「苦の主原因は渇愛、即ち視覚(眼)・音(耳)・臭い(鼻)・味(舌)・触覚(身)・考え(意)の世界に対する欲望である」とブッダは指摘しています。苦(ドゥッカ)の原因は渇愛なので、苦の終焉に至る鍵は渇愛を取り除くことにあります。それ故、ブッダは第三の聖なる真理について、「渇愛の除去」だと説明しているのです。
Ⅳ.第四の聖なる真理 ―苦(ドゥッカ)の消滅に至る道―八正道
四聖諦とは、「苦、苦の原因、苦の消滅、そして苦の消滅へ至る方法」であり、その中にブッダのすべての本質的な教えを含む「象の足跡」です。これら四つの真理の中からどれか一つの真理を取り出して、他のものよりも勝れていると言うようなことは危険なことでもあります。なぜなら、四つの真理はすべて非常に密接に組み合わさって一つのまとまりを作っているからです。
しかし、かりに私たちがその完全なダンマ(真理)への鍵として一つを選び出すとしたら、それは第4の真理、苦の終焉への道でありましょう。それは聖なる八つの道です。その八つは三つの大きなグループに分かれ、八つの要素からなっています。
先ず智慧のグループとして「正見」「正思堆」
次に戒のグループには「正語」「正業」「正命」
そして定のグループの「正精進」「正念」「正定」です。
この八正道はブッダの教えの中でもっとも重要な要素であると言えます。なぜなら、八正道は法(ダンマ)を生きた経験として利用できるようにするものだからです。八正道がなければ法(ダンマ)はただの殻であり、生命のない学説の集まりになってしまうでしょう。八正道がなければ、苦からの完全なる救済は単なる夢になってしまうでしょう。
(1)正見
正見は八正道のすべての要素を案内し指導する「見方」という役割を担っているので、第一番目に置かれています。八正道の実践において、長い道のりを旅して行くための方法を知るために、私たちは正見によって与えられる展望とものごとを理解する力を必要とします。さらに続いて、私たちを目的地に連れて行く他の要素、つまり行為や実行が必要となります。
つまり、実際の行いに着手する前に、私たちの案内人あるいは内なる指導者として、「どこから始め、どこに向かい、実践において一つの段階が過ぎたら次に続くものは何か」を示すために、正見による理解力が必要になります。そのために正見は八正道の最初に置かれているのです。
ブッダは通常、「正見とは四聖諦への理解である」と定義しています。つまり、「苦と、苦の原因、その消滅、そして苦の消滅に至る方法」です。出発点から道を正しく理解するために、私たちは人間の状況について正しい視点を持つことが必要です。
どういうことかというと、私たちの人生において、完全な満足は得られないこと、人生は無常であること、苦に支配されていることを第一に理解しなければなりません。そして苦は、理解によって見抜くべきものであり克服すべきものだということです。娯楽や気晴らしや、心の鈍化による物忘れといった「苦痛の除去剤」によって逃れるべきものではありません。そのことをまずは理解しなければなりません。
もっとも深いレベルで観れば、私たちの存在を作っているすべての物事は五つの集合体(五蘊)です。そしてそれは永続せず、絶えず変化しています。それゆえそれを安全や変わらない幸福のための基礎として維持することはできないのです。ですから、苦の原因はあくまで私たち自身の心の中にあるということです。誰も私たちに苦を押し付けてはいません。その責任を自分たちの外部に置くことはできません。私たち自身が渇愛や執着を通して苦や痛みを生み出している、このことをよく理解すべきなのです。
私たちが、「苦の原因は自らの心にある」と知れば、「苦からの解放への鍵も自らの心の中にある」とわかります。その鍵は智慧による「無知と渇愛の克服」です。そして解放への道に入るためには、「八正道に従って行けば苦の消滅という目的に達することができる」と言う確信が必要です。
ブッダが、「四聖諦に対する理解」として正見を定義したのには大変重要な理由があります。すなわち、弟子たちが彼の教えを単に献身の感情から実践するのでなく、むしろ、彼ら自身の理解に基づいて悟りへの道を歩んでゆくことを望んでいるのです。つまり、人間の生について、その本性を彼ら自身により洞察することです。
あとで次第に分かって来ますが、八正道は正しい理解についての初歩的段階から始まります。実践の中で心が成長するにつれて、理解はしだいに深まり、広がり、そして幅広くなります。そして心が成長するにつれ、私たちは何度も正見に立ち返ってきます。
(2)正思惟
八正道の二番目の要素は正思惟です。思惟のパーリ語「Sankappa」は、「目的、意志、決心、熱望、動機」を意味します。正思惟のこの要素は正見の結果として自然に生まれます。正見を通じて私たちは、生存の真の本質を理解します。この理解により生命の動機や目的や意志と傾向が変わります。結果として私たちの心は邪思惟に対抗する正思惟によって形作られるようになります。
ブッダは、これらの要素を分析し、正思惟には三種類あると説いています。
i)放棄という意思
ii)嫌悪しない、あるいは慈しみという意思
iii)傷つけない、あるいは苦への共感(悲)という意思
これらは三つの不善な心、つまり感覚への欲望、嫌悪、加害や冷酷さという意思に対抗しています。
正思惟は、前にも述べたように、本来的に正見からの結果として生じます。私たちが、苦という事実を洞察して正見を得る時はいつでも、快楽や富や権力や名声への執着を放棄する意思を生じるようになります。これらの欲望を抑圧する必要はありません。欲望は自然に衰えて行きます。
四聖諦というレンズを通して他の存在を見てみると、他者もまた苦の網に捕まっていることがわかります。この認識により、私たちに他者との深い一体化の感情が生まれ、慈しみや苦への共感へと導かれます。これらの態度が起こることによって、私たちのなかに嫌悪や憎悪、暴力、冷酷さを放棄しようという意思が生じます。この正思惟という二番目の要素は、二つの有害な行為の根っこにある「貪欲と嫌悪」を中和するのです。
次の三つの要素により私たちは正思惟を行為に移すようになります。すなわち、正語、正業、正命です。(続く)
比丘 ボーディ『四聖諦』を参考にまとめました。(文責:編集部)

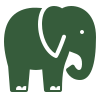 サンガの言葉
サンガの言葉