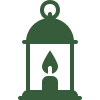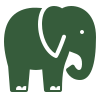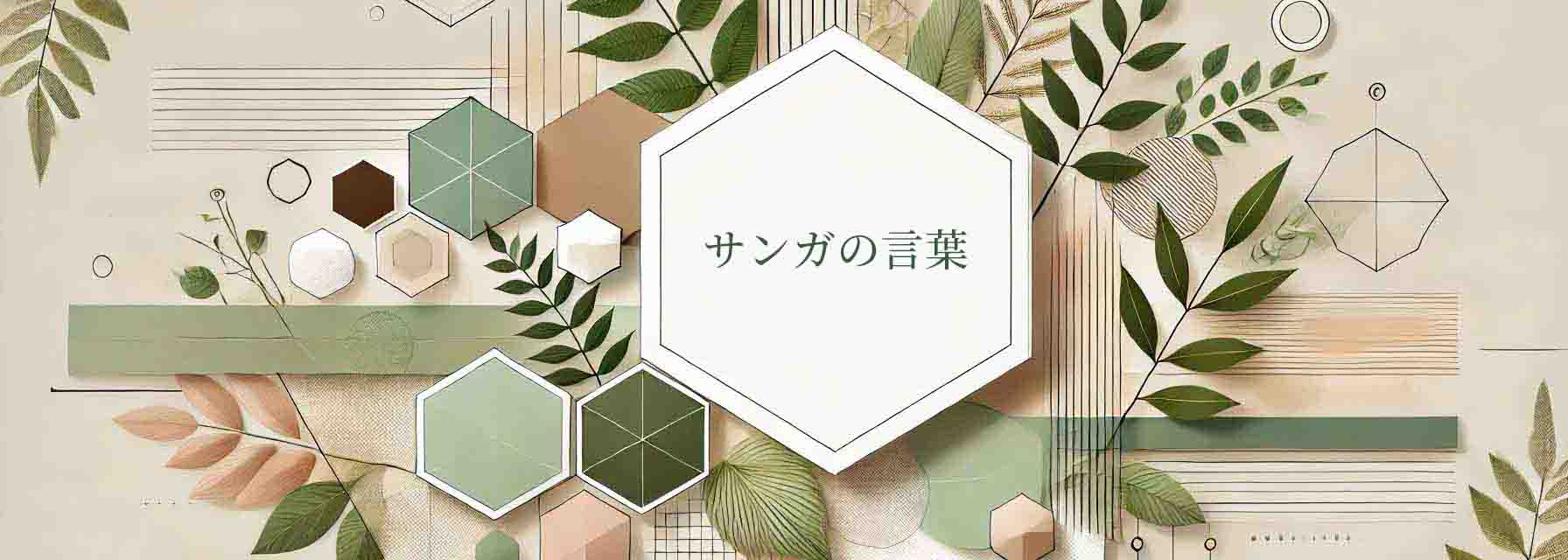人生には上り坂と下り坂とまさかという3つの坂があるとよく言われます。だれも「まさか」が自分の身に降りかかってくるとは思わないものです。私もそうでした。ここでは、私の身に降りかかった「まさか」と瞑想との出会いについて書かせていただきます。
私にとっての「まさか」は、子どもの不登校でした。近年、不登校は年々増え続けており、社会問題にもなっています。でも、まさか自分の子どもが不登校になるとは思ってもいませんでした。しかも地域の公立の中学校ではなく、塾に通い、中学受験までした私立大学の付属中学校でした。当然ながら不登校が続けば、エスカレータ式で系列の高校や大学には上がれなくなります。
「なんであんなに苦労して勝ち取った切符を手放すんだろう。この学歴偏重社会の中で生きていくにはエスカレータに乗っていた方が明らかに有利なのに」。このような思いが私の頭の中を駆け巡りました。まさに合格、入学という天国から地獄への転落という感じでした。
ちなみに私は自分で言うのもおかしな話ですが、自身が遭遇してきた苦難や逆境は乗り越えてきたつもりです。病気などは運命ですし、どうあがいたところで治るものでもありません。それならそれを生きていくための条件ととらえ、自分に与えられた役割を粛々とこなすしかないと考えることができていました。つまり、これまで挫折という挫折はほとんど経験したことがありませんでした。
でも子どものことは違いました。自分の心の持ち方だけではどうにもなりません。感情的に怒鳴ってしまったこともありましたが、冷静に論理的に話しもしました。しかし、思春期の反抗もあり、事態は何も変わりませんでした。将来の夢もかつては体育の先生かプログラマーと言っていたのですが、プロゲーマーやユーチューバーへと変わっていきました。こうなると、私の頭の中をマイナス思考が循環し、ふと気づくと、いつも子供の将来を案じているという状態に陥っていました。おそらくこの頃の私は鬱病寸前までいっていたと思います。
この苦悩に対し、兄弟や親戚も親身になって話を聞いてくれ、心に響くアドバイスもくれました。例えば、「朝が来ない夜はない」「聞くことと待つことが大事」「人間万事塞翁が馬」「神は乗り超えられない試練を与えない」などです。
その中で姉が、「手放す」ことの大切さを教えてくれました。手放すとは、見栄やプライドだけでなく、比較する心も手放すというものでした。確かに私は、「どうして多くの子どもは普通に中学校に通っているのに我が子はそうではないんだろう」という比較からくる悩みに苦しんでいました。「比較する心を手放す」というのは理論では理解できるのですが、心底からは納得できず、葛藤の日々が続きました。
姉が進めてくれたもう1つが瞑想でした。それは、マントラを唱えるサマタ瞑想だったのですが、なぜだか直感的に瞑想が私の苦しみを救ってくれるのではと感じました。心が弱っている時はだれでも藁にもすがりたい気持ちになりますので、そういう側面もあったのだと思います。ひょっとすると、怪しい新興宗教に誘われていれば、入っていたかもしれません。
そこで、瞑想に関する本を20冊近く読みました。その中で、地橋先生が書かれた「心の疲れが消えていく瞑想の不思議な力」という本になぜか魅了されました。この本の中に「子どものためと言いながら、自分が達成できなかった夢を子どもに押しつけている。親の学歴コンプレックスから子どもに無理やり勉強や習い事をやらせている。うまくいかなかった親の人生を子どもを使ってやり直そうとしている。子どものためを装いながら親の自己満足を満たそうとしている。こうした質の悪い愛をいくらもらっても子どもはあまり優しい人にはならないでしょう」と書いてありました。これらの指摘は100%私に当てはまるというわけではなかったのですが、なぜだか心に刺さり、一度この先生に合ってみようと思い立ち、ネットで調べ、初心者講習会に参加しました。その後、1Day合宿と朝日カルチャーセンターの講座も受講しました。(つづく)