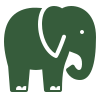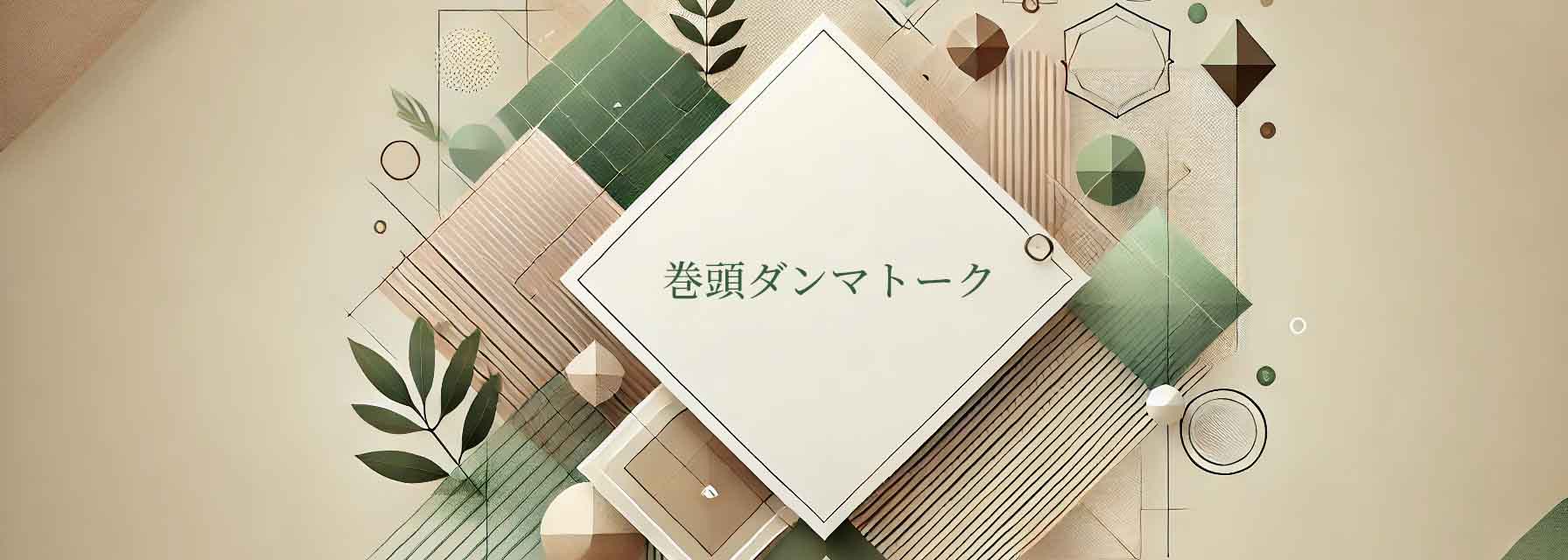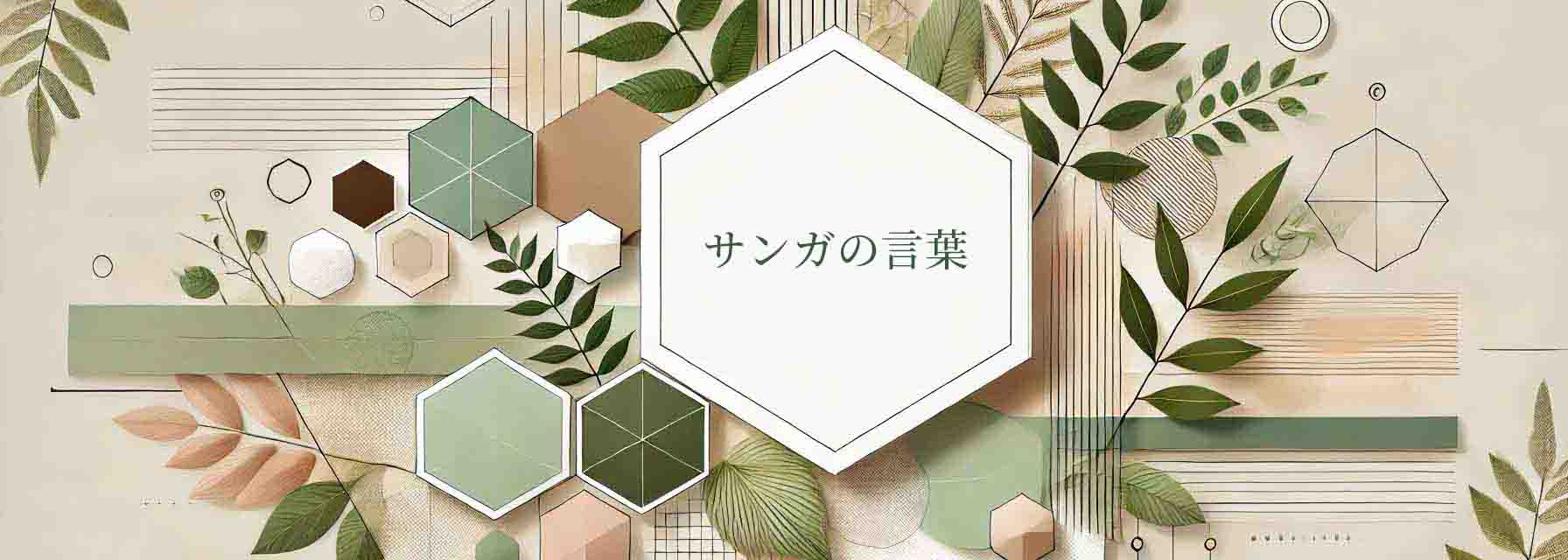編集部より:今月から【懺悔物語】を3回に渡って連載していきます。これは、本誌の読者の目に触れたことのない文書資料で、過去の原稿を執筆当時の文体のまま掲載いたします。
👑「おお、季節よ! 城よ! 無疵な心がどこにある!」(A.ランボー)
大きな悪であれ小さな悪であれ、かつて悪を行なってしまったと自覚している者にとって、アングリマ-ラ尊者ほど心に救いをもたらしてくれる存在はいない。
999人もの人を殺害した殺人鬼でも、仏弟子となり、悟ることができたのか……。それなら、彼ほどの悪をしてはいない私たちにも希望があるだろう。
「以前にはわが手は血に染まり、アングリマ-ラ(指鬘:指の首飾り)として世に知られていた。私がブッダに帰依した姿を見よ。迷いの生存に導く輪廻の環は断ち切られた」(テーラガータ 881)
「悲惨な境涯へ、悪い生存へ、と行かねばならぬ多くの悪行をなし、その悪しき行為の報いにも触れたが、今や私は負債をなくして(托鉢の)施食を受ける身となっている」(テーラガータ 882)
「誰でも、そのなした悪い行為が、善い行為によっておおわれる者は、雲間から出た満月のようにこの世を照らす」(テーラガータ 872)
30歳で修行を開始するまで、頽廃の美を追求しながら酒を飲み、悪いことばかりしていた私は、自身を穢らわしい存在と感じ、罪業感と自責の念から解放されずにいたが、このアングリマ-ラ尊者の言葉にどれほど救われたことか……。
『やってしまったことは仕方がない。私は、償っていこう』と、何度も決意を繰り返していた。
『12年の長きに渡って、私はただ自分のためだけに生きたのだから、これからは人のために生きよう』とも思った。
アングリマ-ラの悟りへの道筋は、清浄道を完成させるために<懺悔>の修行がいかに必要不可欠であるかを物語っている。
この極悪と聖者の両義的資質をもった男がコーサラ国に誕生したとき、生地シュラヴァスティ(舎衛城)の全ての刀槍がギラギラと輝きを放って人の目を射た、とも言われる。
バラモン階級に生まれた聡明で屈強な青年アヒンサ(→アングリマーラ)の悲劇は、同門の学友達の狡猾な中傷誹謗により、師匠の妻と姦通しているという讒言を三度に渡って流されたことから始まった。
別の伝承によれば、端麗な容姿のアヒンサに邪恋の心を抱いた妻が夫の留守中に誘惑したものの拒絶されたことに怒り狂い、自らの衣を破り裂き、アヒンサに乱暴されたと泣いて夫に訴えたからだったとも言う。
「1000人の命を絶ち、その右手の小指を繋いで首飾りとせよ。すでに学ぶべきことを学び終った汝に、それで真の道が備わるであろう」
讒言を真に受け、復讐心をたぎらせた師のこんな狂った命令を、なぜアングリマーラは敢然と実行してしまったのだろうか。
1つには、生来の生真面目な性向があっただろう。
2つには、現代でも「地下鉄にサリンをまけ」というグル(師匠)の言葉を愚直に実行した者たちがいるように、師の命令には絶対服従という外道の伝統の影響がある。
3つには、グルの言葉を聞いた瞬間、兇暴な印象が彼の心に拡がり、無数の因縁の束のなかに眠っていたもう一つの過去世の資質と傾向性が喚起され、邪悪な宿業のドミノが倒れ出してしまったからではないかと思われる。
それは、阿羅漢になれる聖者の素因を持った男の人生が、グラリと暗転していくターニングポイントの瞬間だった。
すべての物事には因果の連続性があり、人は過去の全経験を通して発したエネルギーとまったく無関係のものを突然、何の脈絡もなく発生させることはできない。たとえ自分の命が奪われようとも、たった一人の人間だって殺せない者が大半ではないか。
1000人もの人を殺めるなどという所業が遂行できる者には、そうなるだけの資質も宿業も背景も条件も整った上での必然の力に押しやられる展開があったはずである。縁に触れてしまった業・異熟の塊が、いかんともし難い力で帰結していく因果の構造があっただろうと思われる。
別の伝承によれば、彼のグルはただ指飾りを要求しただけで殺人の命令は下していなかったともいう。死体置場の指でもよかったのに、なぜ彼は大量殺人に走ってしまったのか……。
封印されていた蓋が開けられたかのように、アングリマ-ラの深奥で目覚めてしまった無慈悲と暴力への性向は、人肉を常食とするヤッカ(鬼霊)だったときの過去世に由来するとも言われる。
さらに別の伝承によれば、かつて天界にいたアングリマーラが悠久の時を経て、人間界に王子の身をもって再生したことがある。浄らかな天界にあまりに長く住し過ぎたため、愛欲の煩悩は忘却の彼方に忘れ去られ、その清廉さから<清浄太子>と呼ばれるほどであった。
長じても一向に女性に関心を示さず、国の将来を案じた父王達が一計を案じ、男を迷わす道にかけては国随一の女の巧みな技によって愛欲の煩悩を目覚めさせ、婚姻や世継ぎの誕生に導こうとした。
ある夜、城外ですすり泣く女のか細い声を耳にした清浄太子は、哀れに想い女を招き入れ、仔細を聞くうちにいつの間にか妖艶な女の巧みな技に篭絡され、気づいてみれば男女の関係に導き入れられてしまっていた。
完全な随眠状態だった煩悩に一たびスイッチが入るや、清浄太子は一転、国中の女を漁り尽くすほどの色魔と化し、ついに積年の恨みと怒りが爆発した大勢の民衆の手になる瓦石をもって打ち殺されてしまったのである。
その最期の断末魔の間際にも、両義性の遺志が洩らされたという。撲殺した民衆に必ず復讐する怨念の闇と、いつの世にか必ず悟りを開いてみせるという光の道心だったという。
ジャ-タカの伝によれば、アングリマ-ラの手に落ちた999人の犠牲者はこのとき王子を撲殺したその民衆であったともいう。
こうした伝承の真偽のほどは定かではなく、検証が極めて困難な前生譚や過去世物語などを鵜呑みにできる訳もない。
タイの僧院でお世話になった比丘の師は、コメンタリーに注釈されていないダンマトークは一切しないと言明され、その私見を差し挟まぬ正確さへの潔さに感服したことがある。
しかし同時に、そのコメンタリーがどこまで史実に合致するのか、果たして厳密な検証がなされて伝承されてきたのか……という疑念も浮かんだ。たとえいささかの悪意はなくても、敬愛の念が嵩じれば仏弟子伝にも尾ひれが付き、粉飾されていく危険性は常に免れないのである。
では、どう受け止め、どのように解釈していけばよいのだろうか。歴史に限らず、この世のことは何事も、本当のことは決して見ること能わざる無明長夜の暗昏々たる闇の中に封印されているのがわれわれ凡夫衆生であれば、たとえ作り話であっても、因果論やチェータナー(意志)が具現化していく構造の理解に資するものがあれば、学ぶべきは学んで精進していけば良いのではないかとも愚考している。
ヴィパッサナー瞑想者も真実を確かに見極められる瞬間が到来するまでは、痴や無明の煩悩と悪戦苦闘しながらサティの瞑想を深めていくしかないのだ。
さて、あと一人で1000本の指の満願に達するという時、ついに国軍の出動が発布され、それを知ったアングリマ-ラの母はわが子の命を救おうと彼を目指して近づいていった。
折しもブッダは天眼通の禅定に入り、ことの次第を見渡していた。解脱できる機根を有するアングリマ-ラが満願成就のために母をも殺そうとしている。五逆罪の母殺しをしてしまえば解脱の可能性は断ち切られ、永遠の長きに遠のいてしまう。
すべてを見て取ったブッダはためらうことなく救いに出立した。二人