

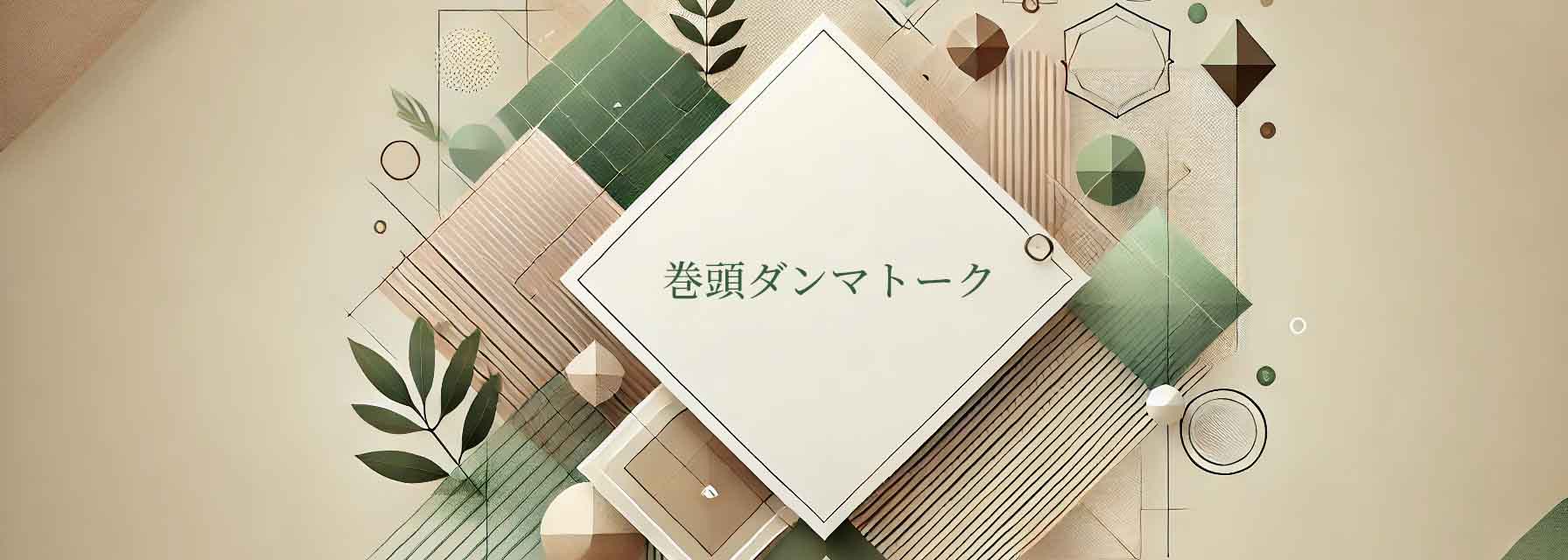



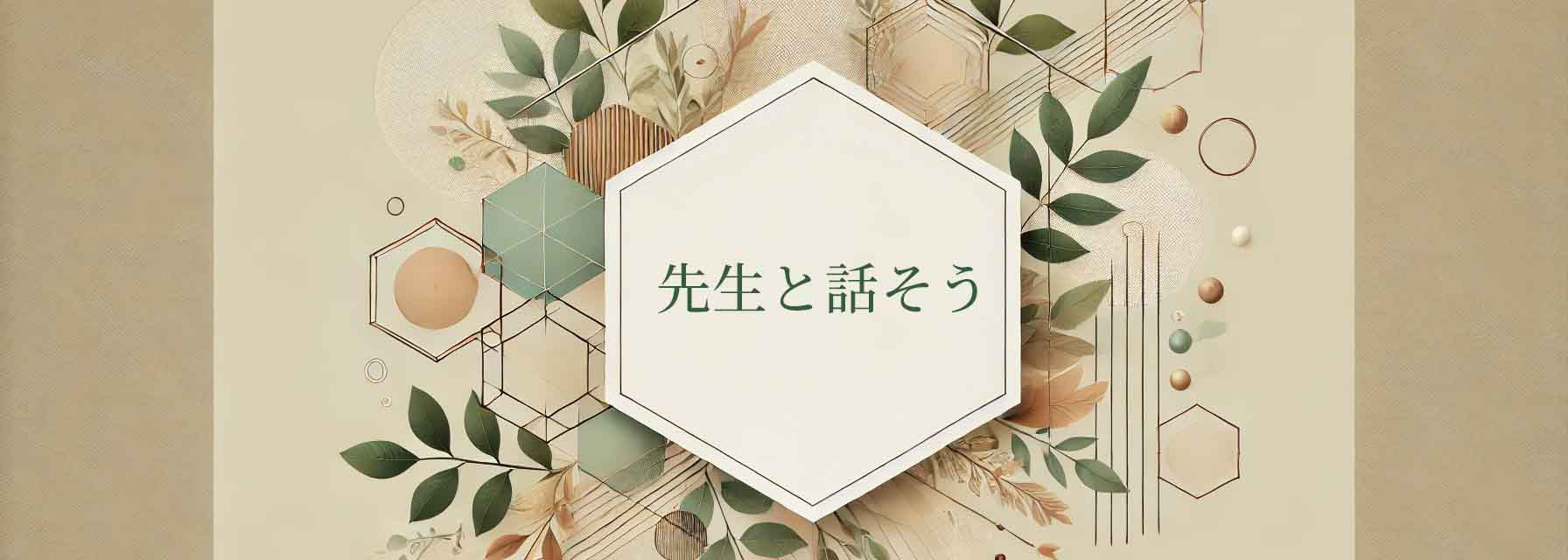
〈ご利益シリーズ〉の三回目、そして最終回です。ヴィパッサナー瞑想をしたらどんなよいこと、すなわち〈ご利益〉があるのかというところから、瞑想をすればまずは集中力と気づきというご利益がもたらされるとともに、苦からの解放につながるのだというお話の序盤までを掲載しました。今回はその続きです。欲望に苛まれている状態とは満たされていないに等しい、ということから話が続きます。
苦諦から生きる喜びへ
榎本 原始仏教では、欲望のとらえ方が世間の常識とは真逆なんですね。
地橋 そうなんです。欲望に囚われている人は、やがて自分が欲望の奴隷状態だったことに気づくのです。どんな欲望も思いどおりに満たされるなんてことはあり得ないし、満たされなければ苦しく、満たされてもたちまち当たり前になって色褪せ、次の人参に向かって走り続けながら皆死んでいくのです。
人生が一切皆苦なのは、妄想のシステムで生きているからです。欲望の対象が甘美に見えるのも、渇愛の執着がエスカレートするのも、ゲットしたものが色褪せて見えてくるのも、何もかも気に食わないのも、諸悪の根源は、妄想にたぶら誑かされ、踊らされ、自らの首を締めていることに無知だからなのです。これが苦諦のスタート地点です。
榎本 ……ということは、このままではまずいと感じた人がグリーンヒルに来るのですね。
地橋 そうです。誰でも最初は、自分の思いどおりに外界を変えようとするんです。パートナーを変えてやろう、同僚や上司を変えてやろうとするが、変わらない。
榎本 どうして変わらないと言えるのでしょう。
地橋 存在の世界・現象の世界は、業の法則と縁起の理法によって展開しているからです。
榎本 (ここはもう少しツッコんで訊いてみたいと思いつつ、それはまたの機会に回そうと思い直して)なるほど。外界に働きかけても変わらないものは変わらない。俺がやろうとしていることは、地面に落ちたリンゴを木の枝に戻そうとしているようなもので、詮無きことだと感じるということですね。すると、自分の心を変えるしかこの苦しみから解放されないのだ、となんとなくわかった人が苦しい人生からの打開を瞑想に求め、グリーンヒルと縁がつく。そういう人たちがグリーンヒルに来たときに、先生はまず何を教えるのですか。やはり、サマーディとサティでしょうか。
地橋 いや、だから、まずはシーラ(戒)を守ることを教えます。
榎本 なるほど、そこでヴィパッサナー瞑想とは戒の瞑想であるということにつながるのか。しかし「まずは五戒を守りなさい」と先生が教えると、その人たちはどういう反応を示すのですか。怒りに身を任せてる人はよくお酒に溺れたりしますよね。
地橋 大抵の場合は素直に従います。そんなのイヤだという人はほぼいない。お酒を飲んだってなんの解決にもならなかったっていうことを、いやというほど経験してきていますからね。そして、五戒を守ることだけでもカルマはかなり良くなります。なんとなく人生が好転している実感をかならず得られるようになるのです。先ほど榎本さんは〈ご利益〉を、集中力や気づきと捉えていましたね。仕事の能力向上に直結したわかりやすいご利益ですが、人生の流れが良くなりはじめた喜びや、因縁にしたがって与えられたものを受け容れていく解放の感覚などをご利益と言わないで、なんと言いますか。
榎本 納得しました。ご利益を機能的にのみ捉えていた私が愚かでした。
瞑想を総合的に捉える
地橋 私はね、瞑想を総合的に捉えているんですよ。
榎本 総合的? サマーディとサティだけでなく「戒」をも含めてということですか。
地橋 いや、もっとスケールが大きいのですよ。……榎本さんは毎月1Day合宿に来られていますが、そこで何をやっていますか。もちろん、サマーディとサティの修行は当然やっているわけですから、それを含めないで答えてください。
榎本 慈悲の瞑想ですね。そしてダンマトークを拝聴しています。
地橋 そうですね。榎本さんはちょっと例外というか毛色が変わっていますが、グリーンヒルに来られる人は人生が苦しいと感じて来る人が多い。そして、そういう人は過去に囚われているケースがほとんどなのです。
榎本 過去ですか。いまの苦しみは過去の体験によるものだという理解でよいでしょうか。
地橋 そうです。人生が苦しくなった原因は必ず過去の問題に端を発しています。幼少期のトラウマ、劣等感の素となったような体験、難しい親子関係や差別やイジメ、甘やかされて自己チューの度合いを激化させていった来し方…。みんな過去の呪縛なんですね。これをきちんと整理しなければならないのに、それをしてこなかったから、今、人生につまず躓くのです。それゆえに、苦しみの解放は、過去からの解放を意味することになります。
榎本 整理はできていないけれども、半分は気づいているわけで、自責の念というものに近いですね。
地橋 なので、握りしめてきたネガティブな過去を手放すために、懺悔の瞑想が実践されるべきなんです。
榎本 ただ、どう考えてもその人ではなく相手のほうが悪いようなケースだってあると思うのです。そういう人は復讐が果たせない悔しさに苦しんでいるわけですね。この場合でも懺悔の瞑想は有効でしょうか。
地橋 そのケースなら、ゆる赦しの瞑想ですね。
榎本 なるほど、しかし、赦せと言われただけで赦せますか。いや、赦さないと苦しいとわかってはいるのでしょうが、なにか理論的なものがないと納得できないのではないでしょうか。
地橋 なぜ恨みや怨念を手放さなければならないか。その理論的根拠が、因果論と輪廻転生論です。徹底的に説明して、必ずネガティブな過去の事実を受け容れる状態に持っていきます。納得がいき腹落ちすれば、瞑想に専念できるのです。禅僧になって7年間、一度も禅定に入れなかった修行者が、母親に対する怨念の由来が読み解け、落涙とともに受け容れた夜、初めてサマーディに入れた事例もあります。
榎本 なるほど。先生が先ほど僕のことを、グリーンヒルの門を叩く者の中では変わり種だとおっしゃられましたが、たしかに僕は興味本位で瞑想をはじめたところがあります。そんな僕がヴィパッサナー瞑想をはじめて、最初に感じた疑問は、どうしてサティを入れるのだろう、なぜ概念を挿し込むのだろうというものでした。これは、瞬間定という言葉で理解できました(「先生と話そう」の5月号参照)。もうひとつは、1Day合宿に来た時に、なぜ慈悲の瞑想をするのか、なぜ個人面接をするのかということでした。一所懸命考えないようにセンセーションに集中しようとしているのに、慈悲の瞑想と面接の時間だけは概念モードになり、瞑想モードが破られてしまうのはもったいないのではという疑問でした。シフトチェンジする意味がわからなかったんですね。けれど、いまお聞きして、サマーディとサティを支えているのは、原始仏教の思想だということがわかりました。
地橋 その通りです。
榎本 ただ、先ほどのケースのような人は瞑想をはじめるまでが大変ですね。
地橋 しかたがない。というか、それが瞑想修行です。
榎本 総合的に捉えるということはそういう意味なのですね。まず戒からはじまる。しかし、慈悲や懺悔や赦しもまた必要である。なるほど…、ということは、ああ、そうか。そのような精神状態で瞑想を行う瞑想者が、今回の話の冒頭で〈育てたい瞑想者のタイプ〉として挙げられていた、〈心を浄らかにする瞑想者〉ですね。しかしそうすると、そのような指導を受けた人たちは、人生が好転していくのを実感できるものでしょうか。
地橋 ものすごくあります。ご利益ありありですよ(笑)。そういう事例を目の当たりにしてきたことが、私のこれまでの情熱を支えてきました。
榎本 となると、先生はほとんど心理カウンセラーですね。
地橋 カウンセラーと瞑想インストラクターを区別する必要もないでしょう。心の反応パターンを浄化しないと、人生の苦しみも瞑想も頭打ちになるんです。苦しみをなくすための教えとシステムが原始仏教なのですから。
聞法による心の変容 経験事象の意味づけの変化
地橋 最後につけ加えたいのは、聞法です。
榎本 聞法? ああ、「月刊サティ!」でいうところのダンマトークですね。
地橋 聞法がなければ、瞑想はできません。かならず暗礁に乗り上げます。
榎本 ほお。なぜですか?
地橋 初心者の一知半解の瞑想理解では、修行が進まなくなるのです。そもそもなぜ瞑想するのかの根本的意義を理解しないと続けられないし、サヤドーやアチャン(先生)たちからより高い知見を得なければ、瞑想のステージを上げていくことが難しくなります。ダンマの理解なしにヴィパッサナー瞑想はできないということを申し上げたい。
榎本 なるほど、それがこの話を始めたときに、先生が苦しみの根源が〈法を理解していないこと〉とおっしゃられていたのにつながるのですね。ところで、聞法は耳学問だと思われますが、読書などもダンマの理解には役に立ちますか。
地橋 もちろんです。
榎本 しかし、ここでもあえて「なぜ」とお訊きしたい。瞑想には知的理解が必要だということをおっしゃられているわけですよね。なぜですか?
地橋 まず、修行の意味を知的に理解しなければならないのです。なぜ戒を守らなければならないのか、なぜ懺悔しなければならないのか、なぜ赦しが必要なのか、なぜいまの自分はこういう状況なのか。因果論をはじめとする仏教の価値観・世界観・パラダイムでこれらのことを理解しないと、ただ言われてやっているだけでは、腹の底から受け容れられないし、たいした〈ご利益〉はもたらされません。
榎本 しかし、先生がそのように説教されると、言われた側はそれを受け入れていくものなのですか、つまり根本的に価値観を変えていくことがあるのでしょうか。知的理解であるとともに、これはもう回心、コンバージョンと言ってもいいようなものですが。
地橋 それを私はやるのですよ。我を張って受け容れなければ、苦しい人生を続けるしかないことを納得させるのです。しかし、と同時に、知的理解だけではだめだということも申し上げておきたい。瞑想という実践とともに知的理解はある。理解したことを人生と瞑想の現場で体験的に検証しながら、この両輪で推し進めていくと、人は変わります。智慧の瞑想としての本領発揮です。経験事象の意味づけが仏教的に変容し、幸福度は確実にあがります。
榎本 ここまでお話をお伺いしてきましたが、ヴィパッサナー瞑想には4つの基盤があるのですね。ひとつ目は戒、ふたつ目は懺悔と赦し、3番目は慈悲、4番目は聞法による知的理解、つまり価値観や人生観の仏教的変容ですね。
地橋 ざっくり言えば四つですが、細かく言えば七つです。①集中力、②気づきによる明晰な認知と自己客観視能力、③五戒による人生好転、④自責の念を乗り超える懺悔、⑤怒りと怨念を解き放つ赦し、⑥慈悲のよろず揉めごと解消効果、⑦聞法による智慧。これを瞑想のご利益・七福神と言ってもよいでしょう。
榎本 七福神ですか、いいですね。(当初は予想していなかったところに話が落ちて驚きつつ)ありがとうございました。

(1)
★速歩の歩行瞑想をしながら夜道を歩いていると、突然高笑いが耳に入り、反射的に「聴覚」とサティが入った。
自分が嘲笑されたのか…という印象が形成されかけたが、強引に断ち切られたと感じた。
ラベリングの言葉は概念だが、それ故に、心に生じようとする概念を消し去る「対消滅」の威力がある……。
……………………
(2)
★ヴィパッサナー瞑想は、エゴの妄想に毒された人類のための技法である。
事実をありのままに知覚するだけなら、ゴキブリも金魚も普通にやっている。
妄想を排除して知覚した瞬間、どのようにラベリングされ認識されるかが問題だ。
ガチャン!
「音」か、「(割れた)イメージ」か、「驚いた」か……。
……………………
(3)
★ラベリングなしのサティでも、現在の瞬間に気づくことができる。
一瞬でも言語脳を使うと、集中を高める仕事がやりづらいと感じる人も少なくない。
身体感覚への気づきはそれでも良いが、微妙な心の動きや意識の流れになると、ラベリング無しのサティでは認知が曖昧になり洞察智が生じにくい……。
……………………
(4)
★法としての事象がありのままに知覚されても、ゴキブリに悟りの智慧は生じない。
危険か餌かに機械的に反応する単純なプログラムでは、事象の本質が洞察されることも、煩悩が全捨てされる衝撃の体験にもなり得ないからだ。
一瞬の経験が、どう認識されたか…。
同じ音、同じ匂いを感じた瞬間、凡夫のラベリングと聖者のラベリングが同じだろうとは思えない……。
……………………
(5)
★認識が確定すると、心は次の瞬間に注意を向ける。
ガチャン!
① 中心対象の感覚に戻るのか、②花瓶を壊した連想に反応するか、③驚いた自分に違和感を持つのか。
一瞬の経験とその認識が、次の瞬間の反応に影響を及ぼす構造……。
……………………
(6)
★瞑想対象に集中しようと必死になっていると、なぜか力んでいる自分の姿が俯瞰され、ハッと我に返ることがある。
サティが本来の機能を取り戻した瞬間だ。
集中にこだわり、ガチガチだった全身からフッと力が脱け、やわらかく緩んでいく。
この脱力の瞬間を「軽安(きょうあん)」という…。
……………………
(7)
★歴史を学び、夢と希望に向かう人もいるし、トラウマに苦しみ、将来不安の妄想で自滅する人もいる。
想像力を持たないチンパンジーは、「今、ここ」だけに心を使いきり、過去を恨まず、未来に絶望することもない。
妄想を止め、サルの脳で経験し、ヒトの脳でラベリングするヴィパッサナー瞑想……。


近く(と言っても歩いて30分くらいはかかるだろうか)に友人が働いているブルーベリー農園がある。大粒のブルーベリーを5種類栽培していて、時々食べさせてもらうが大変美味しい。都会で買う値段からすると格安で分けてもらえる。シーズン中はブルーベリー狩りもできる。
その友人からこんな話を聞いた。ある朝農園に行ったら、ブルーベリーを囲んで設置してしたネットに絡んで鹿が死んでいた。角が立派なオスで、角がネットに絡まって取れなくななったようだ。お尻の肉は動物に食べられていた。狼はもう日本にいないし、この標高だとツキノワグマは下りてこない(今のところは)ので、イタチか、テン、あるいはタヌキの仕業だろう。
オスの成獣だと150キロから200キロと言われる。とても一人で動かせるものではない。彼女はまず近くの農家の直売所のおじさんのところへ走り、地元の猟師さんを紹介してもらった。猟師さん、既に80歳を超えていて、「軽トラックで行ってあげるけど乗せるのはやってもらわないと、腰が無理だから」と言われた。近所から人を呼び集め、4、5人がかりで引きずりながらトラックまで運んだという。真夏ということもあって、死んだ鹿はすぐに腐敗し臭い始める。その上野生動物はどんな雑菌、寄生虫を持っているか分からないので素手で触ってはいけないそうで、軍手をしておっかなびっくり作業をし、その場で作業着は脱いですぐ洗濯機に放り込んだとのこと。彼女も神奈川からの移住者で「野生動物の近くで農業をやるってこういうことなのね」という感想だった。
ちょうどその数日前に、近所で立派な角のオスと、小柄なメスの番を見たところだった。人間など歯牙にもかけない堂々たる佇まいで、悠々と連れ立って森へ帰っていった。あのオスだろうか? と気になったが、どうやらもう少し若いオスのようだった。「ああ、あの鹿じゃない。良かった」と感じている自分。たった一度邂逅しただけで、既に「あの鹿」と「この鹿」に違いが生じ、自分が見た鹿に執着が生まれている。その事にもハッとした。
農業を営むものにとっては、鹿は間違いなく害獣だ。ネットを張ったり、電流が流れる柵を設置したりしている。それでも足りず積極的に罠や猟銃で駆除もしている。鹿も人間も、そしてタヌキやイタチも、自分の暮らしや命を守ろうとしているだけだ。共存など甘い考えだ。このような場所で生活を営んでいて「不殺生戒」を守ることは難しい。しかしそれでも思ってしまう。山にどれだけの鹿がいるだろう。数頭殺すことにどれほどの意味があるのだろう。罠にかかった鹿は、近づいてくる人間を見て殺されることを悟って恐怖するだろうし、子鹿はそれを見ているかもしれない。しかしこれがこの世のシステムだ。食べて食べられて、駆除し駆除される。そうである以上、このシステムから離れる以外にこの痛みから逃れるすべは無いのだ。
その夜、9時を回ったころ、電話が鳴った。同じ事務所に所属していた10歳ほど若い作詞家の急死を告げる電話だった。卵巣ガンの闘病中に急変して亡くなったということだった。いつも前向きで明るい人だった。私の方が先に逝くだろうと勝手に思っていた。人は必ず死ぬ。人の死亡率は100%だ。生き物は必ず死ぬ。様々な死にざまがあり、悲しみや痛みがある。当人にとっても、周囲にとっても。そう思いつつ少しだけ俯瞰してみると、みな生まれて生きて死ぬ道を歩いている訳で、似たような物語を生きている気がする。それから2日間の間に膵臓ガン末期という話と、卵巣ガンで数回目の手術という話を立て続けに聞くことになった。どちらも私よりずっと若い人だった。
全てに偶然は無く、起きることは全て正しく意味がある。――とするならば、鹿の死から始まる一連の死の話は、私が今聞かねばならないことなのだろう。起きることは当人にとってだけでなく、それを受け取る人にはまた全く別の課題となる。ネットに絡んで死に、他の動物に食べられ土に還ることなく人間に処分される鹿の死、病院であらゆる手を尽くした人間の死、今まさに生と死の狭間で格闘している者が見る死、冷徹な言い方をするなら、私にとってそれは、その意味を考えるために与えられた機会なのだ。
テーラワーダ仏教の修行に「死」を見るというものがある。タイの森林僧院で短期の瞑想修行をしていたときに、「比丘たちが死体の解体に立ち合うから一緒に行きますか?」と誘っていただいた。肉体への執着を弱めるための修行のひとつだが、腰が引けて遠慮してしまった。けれど、逃げた課題は、さまざまな姿で私の前に現れる。それは今までの経験から分かっている。「死」を見つめ、生身の肉体への執着を離れる(せめて減じる)ことは、この先修行を進めるために、避けて通れないことなのだろう。
どんなに美しく見える動物も人間も、パーツに分ければ肉と骨と皮と様々な液体だ。肉体は滅びて腐ってゆく。必死に執着しているものを直視すれば、全く違う様相が現れる。「ありのままに見よ」それがヴィパッサナーだ。
八ヶ岳の森は豊かな生と死に満ちている。虫や小動物の死骸はそこかしこにあって、それが生の実相なのだと教えてくれる。まだまだ道は遠いけれど、自らの死も俯瞰して静かに受け止められるようになれたら、と梢を渡る風の音を聞きながら切に思った。


パゴダと念持仏@2025年8月ダモ寺

パゴダ森林背景@2025年8月ダモ寺
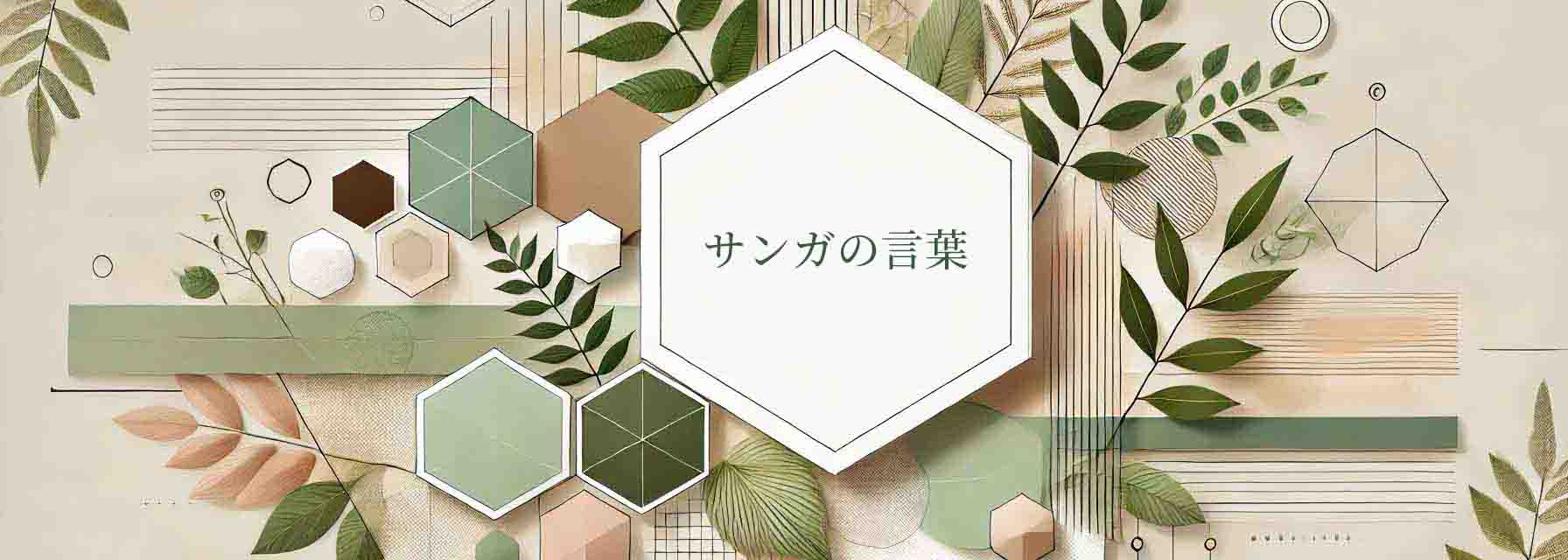
2005年11月から2006年1月に掲載されました。今月はその第3回です。
8.目覚めること
昨日とは昨夜の夢
明日とは今夜の夢
今日とは白昼夢
「感覚の喜びとは、夢のようなものである。人は夢の中で、美しい公園、森の中の沼地、すばらしい風景や池を見るけれど、目覚めた時にはそれらの跡形もない。まさに、感覚の喜びとは、夢のようなものであったのだ」と目覚めた方、ブッダはおっしゃっています。
ブッダは感覚の喜びという、たくさんの夢を伴った輪廻の眠りから目覚めました。夢は感覚の喜びが持つ、人を欺く性質を思い起こさせてくれます。生から生へと、こちらの母からあちらの母の子宮へと、またはある次元の存在から別の次元の存在へと、私たちは眠り続けます。誕生と同時に開くのは肉眼であり、智慧の目ではありません。
私たちは夜夢を見て、日が昇ると目覚めますが、白昼夢は繰り返される生の中でずっと続きます。普段目覚まし時計の音で目覚めるように、死がドアをノックする時、私たちは起こされます。それは私たちが目覚める最後のチャンスです。それは荷造りをする時ではなく、手放す時です。すべての懐かしく、愛しいものからの別れがあり、喪失があり、他のものへの変化があります。
「あらゆる出会いには別れがつきものである」。
夢の中で誰かに会う
だが目覚めるとその人は去っていく
大事に思っている人であっても
人は死に、去っていく
9.あらゆる問題の根
「誤った見方は最大の欠点であると私は言う」
どのような見方をしようが、どのような見解を持とうが完全に各個人の自由なのに、ブッダは何故このように断固とおっしゃっているのでしょうか。確かに自由なのですが、私たちの欠点のすべての根源は誤った「ものの見方」に由来するという事実を否定することができません。これが問題の根です。
種は植え付けられると、実をつけるために大地から水分と栄養分を吸収します。そしてその実は苦かったり甘かったりします。根は種が本来持っている性質に従います。しかしたとえそうであっても、「身体、言葉、心」による行いはその人が持っているものの見方に完全に影響されます。そして良いものであっても悪いものであってもその結果に直面しなくてはなりません。
この真実があるがゆえに、ブッダは弟子たちに次の訓戒を与えられたのです。
「比丘たちよ、間違った見方を持った人の、身体、言葉、心から生ずるあらゆる行為はその人の物の見方と一致する。意志、希望、決意、準備、すべてがその人の内にあり、これらすべてが不快、不幸、好ましくないことへと繋がり、そこからもたらされるものは利益ではなく、痛みである。何故そうなるのか。それはその人の持つ、物の見方が悪いものだからである。比丘たちよ、ニームや苦いヒョウタンや苦いカボチャの種を湿り気のある大地に蒔き、種がいかに大地から水分や栄養分を吸収しようとも、それが分け与えるのは苦味、酸味、不快感である。何故か。比丘たちよ、それは種自体が悪いからである。比丘たちよ、誤った見方を持った人の場合も同じである。その見方自体が悪なのである」
「比丘たちよ、正しい見方を持った人の、身体、言葉、心から生ずるあらゆる行為はその人の物の見方と一致する。意志、希望、決意、準備、すべてがその人の内にあり、これらすべてが喜び、幸福、好ましいことへと繋がり、そこからもたらされるものは利益と至福である。何故そうなるのか。それはその人が持つ、物の見方が良いものだからである。サトウキビやもみ米やブドウの種を湿り気のある大地に蒔くと、種は大地から水分や栄養分を吸収し、分け与えるのは甘味、喜び、おいしさである。何故か。比丘たちよ、それは種自体が良いからである。比丘たちよ、正しい見方を持った人の場合も同じである。その見方自体がよいものなのである」
「種を蒔いたから実を刈り取る。良き行いをした人は良き果実を収穫する。悪しき行いをした人は悪の果実を収穫する」
「不死への門は開かれた。聞く耳を持つ者は信仰を捨てよ」(※註)
ブッダは悟りを開かれてから、すべてのものに対して慈悲心を持って、ブッダの目で世界を御覧になりました。世界は蓮池のように映りました。青や赤や白の蓮の花が咲く池には、水中に沈んだままで水面に上がってこない蓮もあれば、水面に出てきて、その高さのままのものもあります。また水面からかなり上に伸び、汚れのない清らかさを保っているものもあります。他の中の蓮のように、この世の人は心の成長の度合いにおいてさまざまな段階にいます。ある人は鋭く機知に富んでいますが、鈍い人もいます。良い性質を待った人もいれば、悪い性質を待った人もいます。真理を受け入れる人もいれば、そこからしり込みしてしまう人もいます。
蓮がつぼみから満開の状態へと成長していくのとすべて同じです。世間の人も輪廻の中での成長において三つの段階を経ます。
Ⅰ.満足(assada)
Ⅱ.危険(adinava)
Ⅲ.出離(nissarana)
人間は無知に惑わされて、生と死の終わりのない円環の中に満足を見出そうとしています。しかし輪廻というぐるぐる回る「メリーゴーランド」の中で危険を認識する時が来ます。そうすると出口を探し始め、五重奏の管弦楽すなわち、五官の快楽の騒音の渦中でそれらが停止するように求めて泣き叫びます。
「私を真理でないものから真理へ導きたまえ!
私を暗闇から光へ導きたまえ!
私を死から不死へ導きたまえ!」
そのような人たちにブッダは上述のように保証しておられるのです。
「不死への門は開かれた。聞く耳を持つ者は信仰を捨てよ」。
10.自分の「要素」と共にある
私たちは自分の「要素」から離れている時、居心地の悪さを感じます。自分の「要素」と共にある時、安楽な気持ちになります。この安楽さを感じるための最も基本的な条件は四つの要素――地、水、火、風――の知識を持つことです。
私たちは内面・外面の四要素の違いを探すことに夢中になりがちで、それにより自分自身を居心地悪い状態におとしいれています。この世において自惚れや偏見がどれだけ横行していることでしょう。自惚れと偏見でもって外見上の違い――肌の色、形、大きさの違い――ばかりに注目しています。しばしの間熟考して、自らが結局は、「地、水、火、風」のかたまりにすぎないことを知る時、これらすべては表面的で些細なことに見えてきます。私たちはこれらの些細な違いにこだわらずに、「四要素」という普遍的な旗の下に団結することができます。
ブッダは内面・外面の四要素を熟考すれば平静さを得ることができ、安楽と心の平安がもたらされるとおっしゃっています。つまり私たちは自分の周囲の親しい人々や他の生き物と一体なのです。私たちの身の回りの生き物も物質も見た目は多様で鮮明な色彩をしていますが、深く落ち着いて瞑想すると、それらはすべて一つで、本質的には不可分の構造の中にあることが分かります。実は「周囲」という考え方でさえ、一体性という基本概念の中に溶けてしまい、最後には平静さを感じることができます。
そこで私たちに必要なのは、通常的な感覚というこの途方もないものを降ろすために、四つの要素――堅さ、流動性、熟、動き――の性質を、自らの体の部分と働きの中に熟考していくことです。
私たち自身の基本的構造を確信するのに顕微鏡など必要ありません。自分の髪の毛、皮膚、肉、骨は地要素の親類であることがわかります。胆汁、粘液、血液、汗は水要素の一つです。空腹感や熟はその中に火要素があることを認識させてくれます。呼吸により私たちが風要素と共に動いていることが分かります。
「要素を見る」修行が一たび完成すれば、すばらしい安楽な感覚――三次元的世界でさえ、単なる色の艶劇こすぎないような一次元の絵、それも枠組みのない絵に溶解していってしまうという感覚――を得ることができます。(完)
※注:中村元先生は、「恐らくヴェーダの宗教や民間の諸宗教の教条に対する信仰を捨てよ、という意味なのであろう」(ブッダのことば p.431)と解説しています。
(文責:編集部)