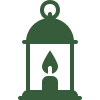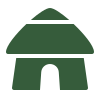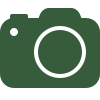私はときどき、知人が怒るまでもないようなことになぜか激怒して、その怒りがかえって本人を傷つけているように見えることがありました。その様子はあたかも、怒りという生き物が怒る理由を自ら捕まえにいっているようにも思えました。決して他人事ではありません。自分にも同じ反応パターンがあるに違いないのです。他の人々はもちろん自分をも傷つけないためにも、怒りを止めることは絶対に必要なこと、私はやってみようと強く思いました。
先生からはたびたび「心の反応系を変える」という言葉がダンマトークで聞かれます。すでにいろいろ工夫されている方もおられると思いますが、私なりの怒りを静めるためのやり方です。もし少しでも参考になるようでしたらぜひやってみてください。頭の整理のため箇条書きにしてみます。
①まず最初に、怒りは周囲も傷つけるけれど、自分自身も不要に傷つけ、判断を誤らせる有害なエネルギーだということをしっかり理解しておきます。
②次に、公憤とか義憤といったものもあります。例えば虐待やいじめで子どもが死亡したり生徒が自殺したりして、児相の不手際や学校の隠蔽体質の情報に触れたときの不快感や怒り、それはまたこちらの正義感の裏返しだとは思いますが、今はそういったことには触れません。今回はあくまで身近の直接的な経験レベルでの話です。
③それでもなお怒りを正義や愛情と勘違いすることもありますから、そこは峻別してきちんと客観視するように努めます。特に親子とか夫婦とか身近な人には難しいのですが、「おまえのため」「あなたのため」というのは本当にそうなのか、自身のエゴはゼロなのかを自分に問うてみます。
④ここからが本題ですが、直接的な怒りにもいろいろなレベルがあります。言葉でも不快から嫌気、憤り、激怒、あるいは怒髪天を突くなどがありますし、また反対に良い印象にも、「悪くない」から積極的な好意までいろいろあります。
このような気持ちをできるだけ客観的に観察する方法として数値化してみます。仮称「好意指数」と「怒り指数」という物差しをイメージして、最高の好意を感じたらマイナス(ー)100、ニュートラルの場合は0、これ以上無いほどの怒りを感じたらプラス(+)100というように。
⑤先ず第一歩として時間と状況を決めてやってみます。私が実践しているのは、通勤の時に改札の5歩手前から始め、電車を乗り換え、降りて改札を出て5歩進むまで、外界に反応した時に生まれた怒りの数値化です。
例えば、改札で誰かと接触して+15(以下+記号は略します)、足と足が触れたので35、旅行者のスーツケースが当たって不快70、踵を踏み飛ばされて痛かった80、前に立ったオジサンがマスクもせずに大きいクシャミで不愉快95など。
それから、老人が杖をついて電車に乗ってきた時に「慈」の心が生まれたのでー20、赤ちゃんの泣き声が聞こえた時には、もし子どもが可愛かったらー40、その泣き声が耳障りに聞こえたら親への怒りで30、オバサンや外国人等の大声での会話がうるさくて63、男子高校生が汗臭くて不快76、などなど。
かなり大雑把ですが、要はその数値自体がどうこうではなく、あくまで上のレベルから見て心の働きを数値化することは、ひいては「好意」や「怒り」を越えて自分の心を客観視する訓練になるのではないかということです。
付け加えれば、私の場合には「0」の感覚を掴んでそれを覚えておくとけっこううまくいくようです。
⑥数値化ができたとして、それからは実際どのように「怒り滅尽の境地」を得るかということになります。私はこんなふうに工夫しました。
・「今日は通勤の時、事故にあってもテロに巻き込まれても何があっても動揺しない」と決意します。好意指数や怒り指数がいくつであっても、「圧、音、色、当たった」などとラベリングしながら0に戻すように努める。
・次に、数値化しなくてもラベリングできるように慣れる。
・このようにしていくと、一時的ではあっても心が完全に静まっている状態を知ることができる。
・そうすると、怒りが生起する瞬間を認識できるようになる。
・認識できれば怒りの生起を止められる。
・怒りの生起を止められると現象に素早く的確に対応できる。
今私が実感しているのは、混んでいる電車で後ろからかなりの圧力で押された時、今まではそこで「何!」となって怒りが起こり、振り返って睨んだり押し返したりという反応が出ていたのが、「(怒り)30」とカウントしたあと「圧」とラベリング出来たら身体から力みが抜けたことです。また、足を踏まれても(カウントを飛び越えて)「当たった」とラベリング。これで痛み自体はあったとしても怒りはスルーして、余計な負担を心に与えることがなくなりました。
これは怒りだけでなく日常生活全般にも応用できると思います。もし余裕があれば「あなたが幸せでありますように」とメッターを送るのも怒りを打ち消すためにとても良い力になると教わっています。
先生についてヴィパッサナー瞑想を始めて半年です。学力、知識も乏しいので少しずつ勉強していこうと思っています。(完)
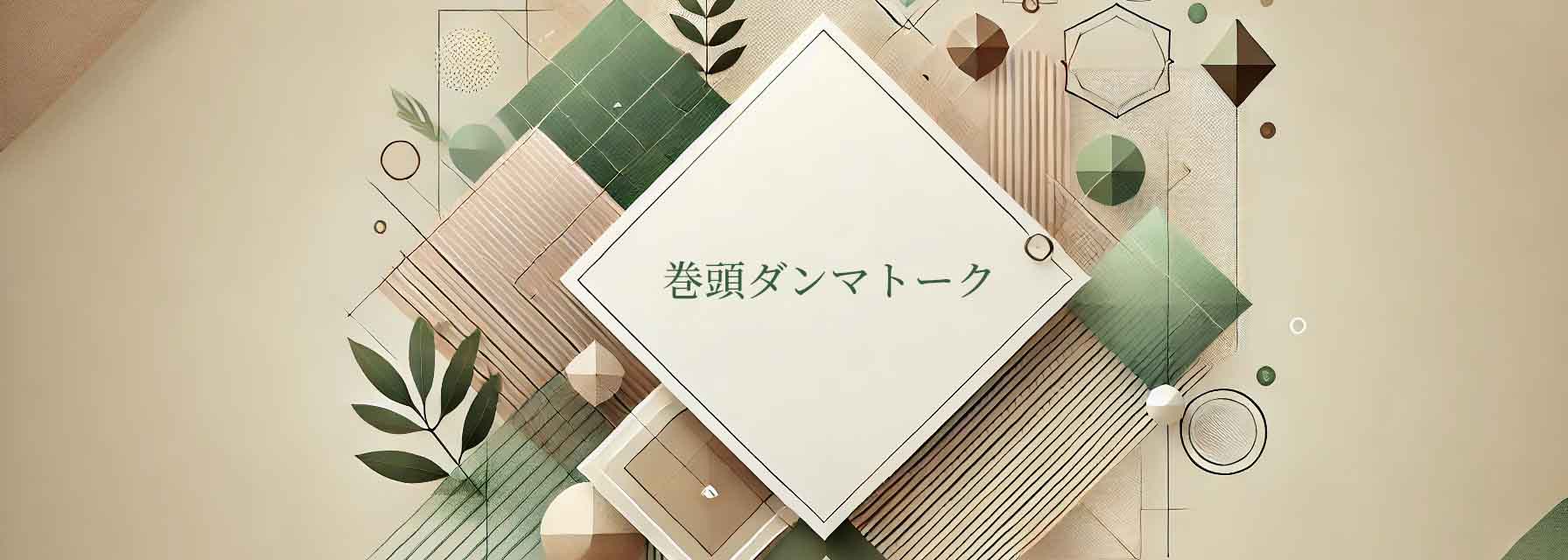
今月はお休みします

『怒りの客観視のための工夫』(後編) 月下るり

暮色を映す上野沼@下館道場から約11km

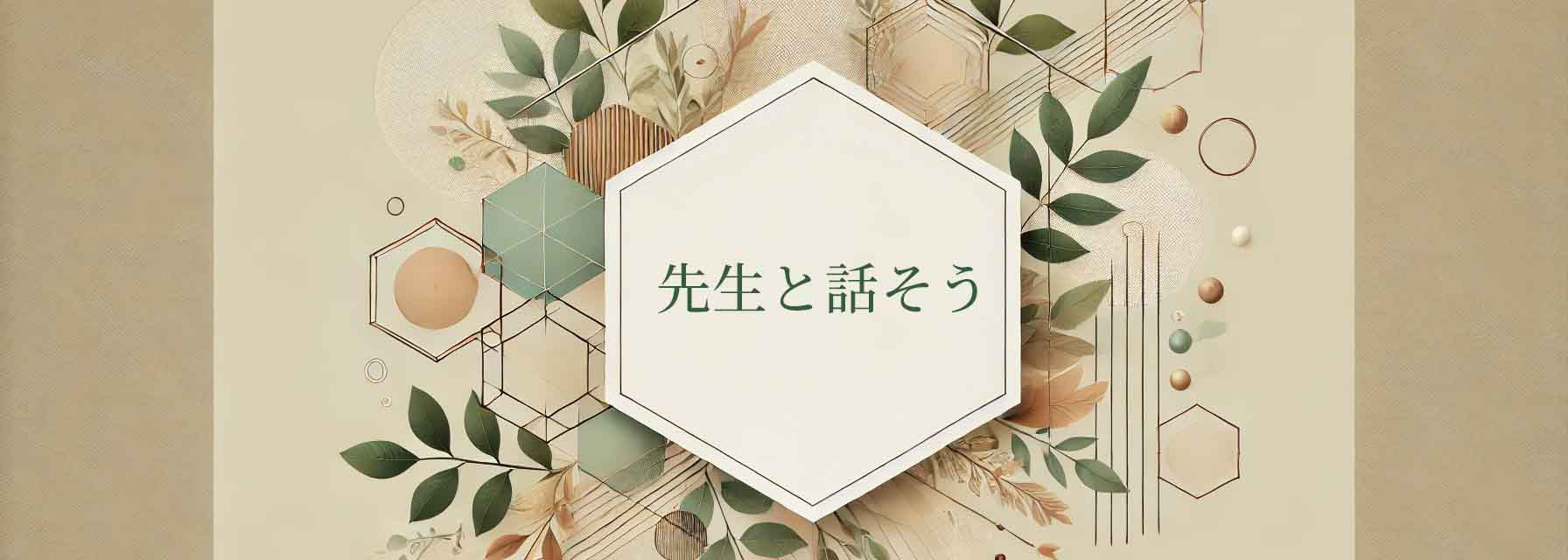
【瞑想と断食】第1回
★今回は、瞑想者がいちどはトライしてみたいと思う断食について、伺います。去年の暮れから今年の1月の下旬まで、地橋先生はまたタイの森林僧院でリトリートを行われました。その際に、先生のほうから副住職のD先生に断食のインストラクションを行ったということを聞いて、このタイミングを逃すまいと思い、お聞きしました。
榎本 三回に渡って、仏寺でのリトリートについてお話を伺いましたが、年末年始にかけて先生はまたタイに行かれたそうですね。
地橋 ええ、12月19日にタイの僧院に入山し、年が明けて1月21日に下山しました。
榎本 瞑想は充実したものになりましたか。
地橋 とても良かったですね。
榎本 今回、X寺副住職のD先生に地橋先生が断食のインストラクションを行ったと小耳に挟んだのですが。
地橋 はい、修行を開始する前に断食をするのが常なので、私と一緒にD先生もなされました。
在家指導者
榎本 在家が出家僧にインストラクションをするというのは希有な例ではないでしょうか。
地橋 いや、そうでもないですね。私の先生だったアチャン・ソンポールという尼さんは瞑想の達人だったので、70人の比丘が住する寺の瞑想指導者をされていてお坊さんからも尊敬されていました。その先生のアチャン・ナエップという在家女性は一来果だったという噂でしたが、出家も在家も指導を仰いでいたようです。大勢の比丘にアビダンマの説法をしている尼さんも見かけました。
榎本 ほお、それはタイだけのことなんですか。
地橋 私が修行したスリランカの森林僧院でも、瞑想のインストラクターは在家者でした。ミャンマーの高名なS.N.ゴエンカも、その先生のウ・バキンも在家者でしたね。出家であれ在家であれ、経験値の高いスペシャリストが後進の指導をする開かれた柔軟さがあるようです。
榎本 在家が僧の指導をするのは意外な感じですが、昔からそんな伝統があったのですか?
地橋 不還果だったチッタ居士は「法を説くことに最も秀でた者」としてブッダが賞賛しています(「チッタ相応経」)。当時から解脱した在家はそうでない僧よりも優れていると見做されましたが、僧を指導する在家という立場が制度化されたことはなく例外的だったと思います。
榎本 在家指導者の存在は最近になってのことなんですね。
地橋 そうですね。20世紀になってからです。ミャンマーで仏教が存亡の危機に立たされたとき、レディ・サヤドーという名僧が在家による瞑想実践と指導の道を開いたのです。「ブッダの法灯が消えるのを防ぐために、在家者も瞑想を修行し、仏法を守る責任を担うべきである」と説き、瞑想を僧院から解放して何千人もの在家者に普及させる立役者になったのです。
榎本 なぜ、ミャンマーの仏教が危うくなったんでしょうか。
地橋 1885年のビルマ王朝滅亡により僧院への国家的支援が失われ、イギリスの植民地支配によるキリスト教が普及し始めたことがレディ・サヤドーの危機感と英断に繋がったのだと思われます。
榎本 お坊さんたちは在家指導者に抵抗を感じなかったのでしょうか。
地橋 レディ・サヤドーは精舎のすべての比丘を召集し、「すべての者よ、よく聞け。この在家者は私の偉大なる弟子サヤ・テッジーである。彼は瞑想を教える能力がある」と宣言し、「今日より、お前は6000人の者にダンマを伝えなければならない」と農夫出身だったサヤ・テッジーに杖を渡したそうです。
榎本 ドラマみたいですね。
地橋 在家も黙っていませんでした。王が不在になったからには我々が仏教を守る、とビルマの在家仏教徒たちが前例のない規模で組織化を始め、在家主導で僧侶の試験を実施して堕落僧や無学僧に圧力をかけ、僧院への布施を集め、仏法研究会を開催し、学識ある僧を認定・顕彰し、キリスト教宣教師の批判に対抗したんです。
榎本 卒啄同時みたいな話ですね。改革する側もされる側も同時に変化してきたタイミングで起きるべきことが起きてくる…。
地橋 そうです。レディ・サヤドーに始まる瞑想復興運動が歴史的転換になった背景には、このような在家仏教徒の成熟があったわけです。仏教は出家だけのものではなく、在家のものでもあることを示唆していますね。
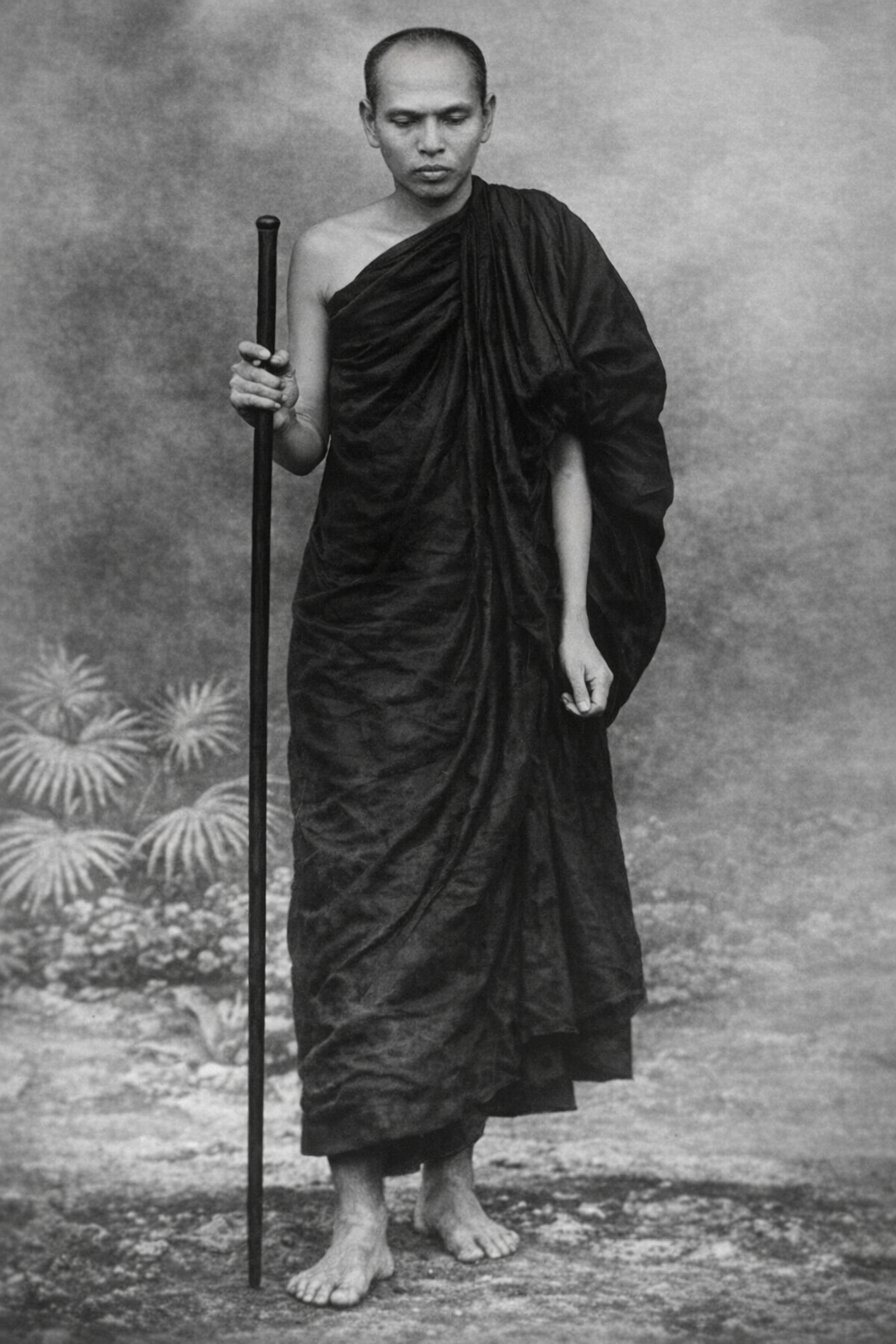
病気治しの断食
榎本 なるほど。…話を断食に戻しますが、先生は常日頃から、食事と瞑想の質はリンクするとおっしゃっていて、心をクリーンにする手法として断食に言及されていますが、原始仏教の教えには断食についての詳細は残っていないのですか。
地橋 ないと思います。ブッダは6年間の苦行を経てこのような行為は無駄であるという考えに達したと言われています。どこの僧院でも断食=苦行と見做され、否定的に捉えられていますね。私は在家なので、制止されても意に介さず断食しながら修行してきました。
榎本 なるほど。では、あらためてお伺いしますが。断食というのは瞑想にはよいものなのですか。
地橋 瞑想には体力勝負の一面があります。体の状態が変われば心も変化するので、まあ有効ということになりますが難しい、と言うか、面倒というか厄介ですね。そもそも断食中は瞑想できないことが多いです。
榎本 え、そうなんですか。
地橋 人によりますが、断食が進行し低血糖状態になればヘロヘロになり大抵は瞑想できませんね。それも断食中のデトックス(解毒)の個人差が大きいので予想がつきません。断食で2日ムダになっても、その後に挽回すればよいだろうと考えてやることになります。
榎本 今回D先生が断食をされた目的は何だったのでしょうか。やはり、瞑想を高めるためですか?
地橋 いや、D先生の場合は健康のためです。胃炎なのか潰瘍なのか、長い間、胃痛に苦しんでおられたんです。制酸剤を服用していましたが、対症療法で治るはずもないので、断食なら根本治療になりえると、私が勧めました。念のためAIで調べたら、70過ぎの老比丘に本断食などトンデモナイと全面否定でしたね。それをD先生にお伝えしたうえで決心していただいたのです。
榎本 地橋先生には自信がおありだったのですか。
地橋 ええ、断食の威力は熟知していますから。私は医学番組をよく観るので、絶食が一定時間を越えると胃壁の微細な傷が修復されやすくなるのを知っていました。胃粘膜の防御機構が絶食時に再編成されるのです。消化管全体で構造変化を引き起こし、粘膜の厚さや細胞構成が変わるのですね。これが根本治療に通じるだろう、と。また、AIはネットから情報を集めてくるので、ネットには、断食の知識のない医者の情報が氾濫している。否定されるのは当然ではないかとも申し上げました。
榎本 それで、D先生はどうなりました。
地橋 大成功と言ってよいのではないでしょうか。胃の痛みがゼロにまではなりませんでしたが、10分の1にまで激減し、想定通りでした。断食中に真っ黒いタール状の便がたくさん出て、便器にへばり付いてなかなか取れなかったとも仰っていました。医学的には「宿便」は存在しないことになっていますが、腸粘膜の剥がれたものや腸内細菌の死骸、胆汁の濃縮物などが混ざった腸の垢のようなものと考えられています。一抹の不安もありましたが、結果的にその他の体調不良要因もセットで改善され、断食療法の面目が保てました。
対機断食
榎本 それはよかったですね。少し話が逸れますが、グリーンヒルが10日間の合宿を行っていたころは、断食のコースもあったとか。
地橋 いや、そんなものはありません。ここは瞑想道場であって、断食道場ではないと言明していましたから。それでも、修行時代は48時間の短期断食を1年に50回もやるほどのマニアでしたから、ダンマトークでつい話してしまう。すると瞑想がなかなか進まない参加者がなんとかしたいと断食を希望するので、やむなくインストラクションしていたのです。
榎本 ざっくり言うと、大体どういうスケジュールになりますか。
地橋 修行時代に断食の先生から伝授され、自他の経験データを積み重ねながら開発した私流の断食は48時間が目安です。いきなり断食を開始するのではなく、2日ぐらい前から階段を下りるように減食し、断食後はその倍以上の時間、およそ1週間かけて復食します。多くの人が生半可な知識で勝手に断食を試みるものの、さしたる効果が得られないのは緩やかに戻していく復食がデタラメだからなんです。しかも断食は個人差がメチャクチャ大きいので、定型のコースをマニュアル化しづらいのです。合宿中は私が参加者をつぶさに観察して、対機説法のように、これをこれだけ食べなさいとマンツーマン指導するのが常でした。
榎本 今回のD先生に対しても同じことをされたのでしょうか?
地橋 はい。断食中にはこういう症状が現れるかもしれないということも話しておき、異常があればいつでもメール指導する体制を取りました。復食が始まってからは、食堂の食事供養の際に私がD先生の召し上がってよい分量をタッパーに取り込み、それを改めて供養するやり方をしました。
榎本 もし復食がいい加減だと、どうなりますかね。
地橋 2、3日の断食だったら荒っぽい解き方をしても死ぬことはありませんが、長期断食になれば、いきなり肉団子のスープを飲んで死んだロシア人がいたと言われています。
榎本 (絶句して)死んだんですか。
地橋 断食直後に普通食をとって死亡することを「リフィーディング症候群」と言うのですが、電解質が細胞内へ急激に移動すると血中濃度が急低下し、心不全を筆頭に肝機能障害や多臓器不全で死んだ事例が多数報告されています。
榎本 いや、驚きというか、諸刃の剣ですね…。

2026年2月号
(1)
★快いものを貪り求め執着する本能を、自然搭載して生まれてくるのが生命だ。
一方、胎児の手指や幼児期の脳神経細胞、免疫細胞の9割には、次々とアポトーシス(プログラムされた細胞死)が起き、生命の最適化が計られる。
貪り求めるのも(足し算)、手放すのも(引き算)、どちらも根源的な生命のシステム……。
……………………
(2)
★人生が思い通りにならないのは、自分が作った膨大な業が否応のない力で現象化し、日々展開してくるからである。
簡単に変えられるものもあるが、ごくわずかだろう。
それ故に、嫌なことでも起きたことはそれで良しとし、心汚さず、流れに身をまかせて認知を変えることができれば苦は減少する……。
……………………
(3)
★新型ウイルスの感染であれ怪我や事故であれ、身体に苦受を受けた瞬間、殺生戒系の不善業が一つ消えていく……。
ありがたいではないか。
風評に踊らされ、不安や恐怖の妄想に怯えれば、ストレスホルモンが分泌して免疫力が低下するだけだ。
いかなる時にも瞑想し、心静かに、腹を括っておく覚悟……。
……………………
(4)
★感謝すべき楽受の日々よりも、苦しかった時期に多くの深い学びを得てきた。
楽しいのも苦しいのも、どちらも等しくありがたいことだが、しょせん事実をそのように認識しただけのことではないか。
常に脳内フェイクを生きてきた私も、人には真実は見られないのだ、とこの歳になり腹に落ち、心に沁みてくる……。
……………………
(5)
★解脱した聖者でも、業が帰結する力に抗うことはできない。
2度刺客から逃れた目連尊者も3度目は凶刃に倒れ、ブッダも怪我をしたり罵詈雑言を浴びせられた。
病むのも死ぬのも、因縁があれば必ずそうなってしまうのが業の異熟(現象化)だ。
因果論を心得て、起きたことは受け容れるしかないと腹を括る。
なすべきことをなし、慌てず騒がず、瞑想する……。

寒い!
年が明けて、熊の目撃情報も無くなった。それはそうだろう。寒い、寒すぎるからだ。 熊でなくても冬眠したいぐらいの寒さである。
家のリフォームをしている時、大工さんに手すりを頼んだ。「ステンレス製、木製、樹脂製があるが、ステンレス製は止めた方が良いですよ。うっかり手袋無しで触ると皮膚がくっついてしまって大変です。」と言われた。その時は「ふ~ん、そんなものか。」と聞き流したが、さもありなん、である。
12月のクリスマスの頃は、キンキンに冷えた空気が澄み渡って、山は美しく大きく近く見え、星空は凍るように瞬き、霜柱をサクサク踏んで歩くのも嬉しいくらいだった。その頃で零下2、3℃だったのではないか。
年明け、窓からの冷気は窓際に座れないほどになった。風呂場は冷蔵庫として使えるくらいだが、水道の蛇口からチョロチョロだしておいた水は、朝には止まっている。冷蔵庫というより冷凍庫である。
朝、車に乗ろうとしたら、フロントガラスは霜で真っ白。しばらくエンジンをかけて温めようと思ったがドアが凍りついて開かない。泣きそうになった。近所に住む東京からの移住組によれば、うっかり車に野菜を置き忘れたら、翌朝にはみんな凍っていたそうだ。その日の最低気温は零下10℃。
むかし暮らしたフランクフルトの冬を思い出す。やはりフロントガラスが凍っていて、ご近所はみんなガリガリと引っ掻いて氷を落としていた。「お湯をかければ良いじゃないの?」と思って家から沸かしたお湯をたっぷり持ってきてざあっとかけた。どうなったかというと・・・まるで飴が溶けて固まったように、硬い氷になって頑固にフロントガラスに張り付いてしまった。「そんなことをやった人は見たことがない。」とご近所さんには呆れられ、その日は午後になるまで車には乗れなかった。その時の経験が無ければ、今回も同じことをやっていただろう。ただし、フランクフルトのアパートのような家は建物全体が温められ、家の中は巨大なデロンギが備え付けてあって、中は半袖でアイスクリームを食べられるくらい暖かかった。
ひるがえって八ヶ岳の家は寒い。前述のように風呂場は冷凍庫だし、北側にあるトイレも洗面所も冷えている。夜中に起きてトイレに立つのを我慢したくなるほどだ。12月の末にトイレ用に小さなセラミックヒーターを入れたが、10℃になるのがやっとだった。リビングには巨大な灯油のファンヒーターが付いているのだが、こちらはさすがに強力で、部屋を暖めてくれる。200Lのタンクが10日ほどで空になる勢いだが、凍死するよりマシだと腹をくくって、ガンガン焚いていた。すると夫が「喉がおかしい」と言い出した。そう、FF暖房機を使うと乾燥するのだ。ただでも雨の少ないこのエリア、今年はまた極端に雨が少なく、毎日地元の消防署か消防団が域内放送で「林野火災警報が発令されました」とやっている。そんな警報があることさえ知らなかった。
加湿器をつけたが焼け石に水。仕方ないので洗濯物を部屋中に干してみた。それでも湿度計は「LL」(極少という意味だろう)、「いっそこれでどうだ!」とばかりに、洗う必要ないタオルケットやシーツ、バスタオルを濡らして干しまくった。それでようやく30%に届くか届かないか。とうとう地元のホームセンターに走り、ダルマストーブのような、天板に鍋が乗せられるタイプの大型の石油ストーブを買ってきた。「これなら大丈夫だろう」と喜び勇んで点火。まあ暖かいのだが、予想していたようにグラグラお湯が沸くという感じでは無い。燃え方も東京で使っていた感じと全く違う。
なぜだろう? 何か設定が…と取説を読んでいて小さな文字が目に入った。「標高1,000m以上の場所では使用不可」そうか。登山する友人が山の上ではコーヒーが沸かせないと言っていたことを思い出した。酸素が薄いのだ!我が家の標高は950m。ギリギリセーフというところだが、平地のように景気よく燃えてはくれないようだ。
ええい、ままよ、と家中の電気暖房機を点けまくった。ホットカーペット2枚、デロンギ、電気毛布、電気座布団、加湿機能付き暖房機、当然加湿器も稼働。トイレのセラミックヒーター、ペット用のホットカーペット。さらに、お湯を沸かそうと電気ポットのスイッチを押した途端に、ブレーカーが落ちた。停電。真っ暗になった。容量オーバーだ。灯油のファンヒーターまで止まってしまった。燃料は灯油だが、電気で温度設定やタイマーがかかるので、停電したら動かない。真っ暗の部屋の中で静かに大人しくオレンジ色の光を輝かせながら、ダルマストーブだけが生きていた。ああ、ダルマストーブ! あなただけが頼りよ、と親近感が湧く。
二重窓にするしかない、と決心して馴染みの大工さんに連絡したが、急には手配できないとのことで、当面はこのまま頑張るしか無いということになった。外構工事や手すりなどより窓が先だったと悔やむが、後悔先に立たず。我が家は、吹き抜けの2階までの大きなガラス窓で、今から思えば全く夏仕様の家だったのだ。
涙ぐましい奮闘に天も哀れと思ったのか、今日は少し温かかった。最高気温が0度を超えていた(1℃だけれど)。耳がちぎれそうな八ヶ岳下ろしの風もいくぶんおだやかだった。体もだんだんに慣れてきたのかもしれない。けれど、寒さの本番はこれからの1ヶ月だ。最低気温は零下15℃くらいになるらしい。こんなにも春を待ちわびる冬を体験したことはいままで一度もなかった。

タイ森林僧院ウィハーン(仏殿)のブッダ像